ハクビシンの侵入口を完全に封鎖するには?【金網とシーリング材が有効】DIYでできる3つの封鎖テクニック

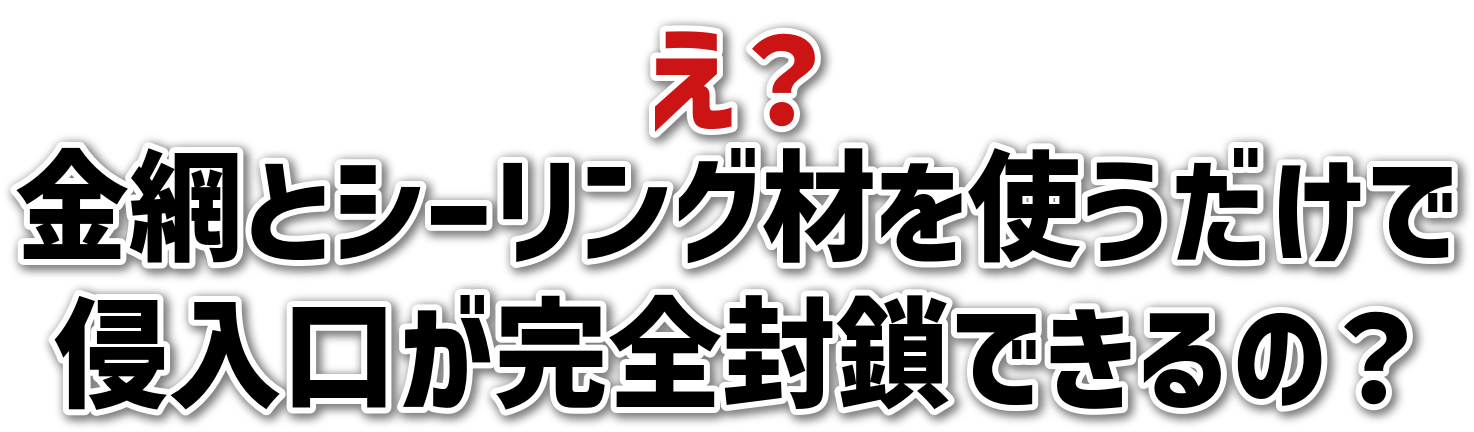
【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの侵入に悩まされていませんか?- 侵入口の特定方法と効果的な封鎖材料の選び方
- 金網とシーリング材を使った完全封鎖のステップ
- 封鎖後の点検と管理の重要性
- DIYの危険性と専門知識の必要性
- ハクビシンを寄せ付けない5つの驚きの裏技
この厄介な訪問者を完全に締め出すには、金網とシーリング材を使った適切な封鎖が鍵となります。
でも、「どうやって侵入口を見つけるの?」「正しい材料の選び方は?」と不安になるのも当然。
本記事では、プロ顔負けの封鎖テクニックから、意外と効果的な裏技まで、ハクビシン撃退の全てをお教えします。
さあ、一緒に安心で快適な住まいを取り戻しましょう!
【もくじ】
ハクビシンの侵入口を完全に封鎖!金網とシーリング材の効果

侵入口の特定!「足跡」「爪痕」「糞」がカギ
ハクビシンの侵入口を見つけるには、足跡、爪痕、糞などの痕跡を探すのが一番効果的です。まずは家の周りをじっくり観察してみましょう。
「あれ?ここに何かの足跡がついてる…」そんな違和感に気づくことが、侵入口発見の第一歩です。
ハクビシンの足跡は、猫のものに似ていますが、少し大きめです。
5本の指がはっきりと残っているのが特徴です。
次に注目したいのが爪痕。
ハクビシンは木登りが得意なので、家の外壁や樹木に爪痕が残っていることがあります。
「ガリガリ」と引っかいたような跡を見つけたら、そこから上を見上げてみましょう。
屋根や壁の隙間に侵入口があるかもしれません。
そして忘れてはいけないのが、糞の存在です。
ハクビシンの糞は、バナナ状で長さ3〜5センチほど。
黒っぽい色をしていて、独特の臭いがします。
「うわっ、この臭い…」と思ったら要注意。
糞が見つかった場所の周辺を重点的に調べてみましょう。
- 足跡:猫より少し大きめ、5本指がくっきり
- 爪痕:外壁や樹木に「ガリガリ」とした跡
- 糞:バナナ状、長さ3〜5センチ、黒っぽい色
屋根裏や外壁の隙間、換気口などを重点的に調べるのがコツです。
「ここから入ってるのかも…」と思ったら、夜間に赤外線カメラで監視してみるのも効果的。
ハクビシンの動きを確認できれば、侵入口の特定は間違いなしです。
金網とシーリング材が有効!侵入を防ぐ最強コンビ
ハクビシンの侵入を完全に防ぐなら、金網とシーリング材の組み合わせが最強です。この二つを使えば、ガッチリと侵入口を封鎖できるんです。
まず金網ですが、これはハクビシンが噛み切れないようにするためのものです。
「えっ、金網くらい簡単に噛み切れるんじゃ…」なんて思った方もいるかもしれません。
でも、ちゃんとした金網を使えば大丈夫。
ステンレス製で目開き1センチメートル以下、線径1.5ミリメートル以上のものを選ぶのがポイントです。
こんな感じの金網を侵入口にしっかりと取り付けます。
でも、金網だけじゃまだ不十分。
ここで登場するのがシーリング材です。
シーリング材は、金網と壁の隙間を完全に埋めてしまうすごい奴なんです。
「シーリング材って、お風呂場とかで見るアレでしょ?」そう、まさにそれです。
でも、ただのシーリング材じゃダメ。
ハクビシン対策には、耐候性と耐久性に優れたシリコーン系やポリウレタン系のものを選びましょう。
これらは紫外線や雨風に強く、長期間しっかりと効果を発揮してくれます。
- 金網:ステンレス製、目開き1cm以下、線径1.5mm以上
- シーリング材:シリコーン系かポリウレタン系
- 組み合わせ効果:物理的遮断+隙間完全封鎖
「これで安心して眠れる!」そんな日々が待っているはずです。
でも、施工には少しコツがいるので、自信がない場合は専門家に相談するのがおすすめですよ。
シーリング材の選び方!「耐候性」と「耐久性」に注目
ハクビシン対策にピッタリなシーリング材を選ぶなら、「耐候性」と「耐久性」がカギになります。この二つの特性をしっかり押さえておけば、長期間効果を発揮する封鎖ができるんです。
まず「耐候性」ですが、これは外部環境に耐える力のこと。
「え?シーリング材って屋外で使うの?」なんて思った方もいるかもしれません。
でも、ハクビシンの侵入口は屋外にあることが多いんです。
だから、紫外線や雨、風、温度変化にも負けないシーリング材を選ぶ必要があります。
次に「耐久性」。
これは長期間変質せずに、機能を維持する能力のことです。
「いくら頑丈でも、すぐにボロボロになっちゃったら意味ないよね」まさにその通り。
だからこそ、長期間硬さと弾力性を保てるシーリング材を選ぶのがポイントなんです。
具体的には、シリコーン系とポリウレタン系のシーリング材がおすすめ。
この二つは、それぞれ特徴があります。
- シリコーン系:紫外線に強い、耐熱性が高い
- ポリウレタン系:伸縮性に優れる、塗装が可能
実は、場所によって使い分けるのがコツなんです。
例えば、直射日光が当たる場所ならシリコーン系。
建物の継ぎ目など動きがある場所ならポリウレタン系、といった具合です。
選ぶときは、パッケージに書かれている特性をよく確認しましょう。
「屋外用」「耐候性」「耐久性」といった言葉が書かれているものを探すのがおすすめです。
値段は少し高くなりますが、長期的に見れば、頻繁に塗り直す手間と費用が省けるんです。
「これで完璧!」なんて思わずにいてください。
実は、シーリング材の塗り方にも秘訣があるんです。
でも、それはまた別のお話。
とにかく、耐候性と耐久性に優れたシーリング材を選べば、ハクビシン対策の第一歩は踏み出せたも同然です。
隙間を見逃すな!10cm以下の穴でも要注意
ハクビシンの侵入を防ぐなら、小さな隙間も見逃してはいけません。なんと、直径10センチメートル以下の穴でも、ハクビシンは難なく通り抜けてしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いでしょう。
ハクビシンは体を縮める能力が驚くほど高いんです。
まるでゴムみたいに体をクニャクニャと曲げて、小さな隙間をすり抜けていきます。
「スルッ」とね。
だから、一見大丈夫そうに見える小さな隙間も、ハクビシンにとっては立派な侵入口になってしまうんです。
では、具体的にどんな場所を注意すればいいのでしょうか?
ここで、要注意ポイントをいくつか挙げてみましょう。
- 屋根と壁の接合部
- 換気口やダクト周り
- 配管の通り道
- 外壁のひび割れ
- 軒下や破風板の隙間
「え?こんなに小さな隙間、大丈夫そうだけど…」なんて思っても油断は禁物。
ハクビシンの侵入を完全に防ぐには、1センチメートル以上の隙間は全て塞ぐくらいの気持ちで臨むのがコツです。
隙間を見つけたら、すぐに対策を。
金網とシーリング材を使って、しっかりと塞いでいきましょう。
特に注意が必要なのは、屋根裏への侵入口。
ここから侵入されると、家全体に被害が広がる可能性があるんです。
「でも、全部の隙間を見つけるのは大変そう…」そう思った方、安心してください。
確かに一人で全てをチェックするのは難しいかもしれません。
そんなときは、家族や友人に協力してもらうのもいいアイデアです。
複数の目で確認すれば、見落としも減りますよ。
最後に、定期的なチェックの重要性も忘れずに。
建物は時間とともに劣化し、新たな隙間ができることもあります。
「よし、これで完璧!」と思っても、半年に一度くらいは全体をチェックする習慣をつけるのがおすすめです。
小さな隙間も見逃さない。
これが、ハクビシン対策の基本中の基本。
「ちりも積もれば山となる」ではありませんが、小さな対策の積み重ねが、大きな効果を生み出すんです。
DIYは危険!「専門知識」と「技術」が必要な理由
ハクビシンの侵入口封鎖、「自分でやっちゃおう!」なんて思っていませんか?でも、ちょっと待ってください。
実は、この作業、専門知識と技術が必要なんです。
DIYで挑戦すると、思わぬ危険が待っているかもしれません。
まず、屋根や高所での作業は非常に危険です。
「ちょっとくらい大丈夫さ」なんて油断は禁物。
転落事故のリスクは想像以上に高いんです。
専門家は安全器具の使用方法を熟知していますが、素人が同じことをするのは非常に危険。
「ズドーン」なんて音とともに転落…なんてことにもなりかねません。
次に、建物の構造に関する知識も必要です。
「ここを塞いじゃえば完璧!」なんて思っても、それが建物の重要な換気口だったら?
湿気がこもって、カビの温床になってしまうかもしれません。
「えっ、そんなことになるの?」ってビックリしますよね。
そして、適切な材料の選択と使用方法も専門的な知識が必要です。
先ほど説明した金網やシーリング材も、正しく使わないと効果が半減。
「せっかく頑張ったのに…」なんてガッカリする結果になりかねません。
- 高所作業の危険性
- 建物構造への影響
- 材料の適切な選択と使用
- 法的規制への対応
実は、害獣対策にも様々な法律や条例が関係しているんです。
「えっ、ただの害獣対策なのに?」って思うかもしれません。
でも、方法によっては違法になる可能性もあるんです。
専門家は、これらすべての知識を持っています。
だからこそ、安全かつ効果的な対策ができるんです。
「でも、お金がかかるんでしょ?」そう思う方もいるでしょう。
確かに初期費用は高くなるかもしれません。
でも、長期的に見れば、効果的な対策による被害防止と、安全性の確保がコストを上回るんです。
「よし、専門家に任せよう!」そう決心したら、信頼できる業者を探しましょう。
実績や評判をしっかりチェックして、納得のいく説明をしてくれる業者を選ぶのがポイントです。
そうすれば、安心してハクビシン対策を任せられるはずです。
効果的な封鎖作業!ステップバイステップで完全防御
清掃から始めよう!侵入口周辺の徹底洗浄が重要
ハクビシンの侵入口を封鎖する前に、まずは周辺をキレイにすることが大切です。これが封鎖作業の第一歩なんです。
「えっ、掃除から?」って思った方もいるかもしれませんね。
でも、これには重要な理由があるんです。
ハクビシンは嗅覚が鋭くて、自分の匂いのする場所に戻ってくる習性があります。
だから、その匂いを完全に消し去ることが大切なんです。
まずは、侵入口周辺のゴミや落ち葉をキレイに取り除きましょう。
次に、水で洗い流すんです。
でも、ただ水をかけるだけじゃダメ。
中性洗剤を使って、ブラシでゴシゴシ洗うことが大切です。
「こんなに丁寧に掃除しなきゃダメ?」って思うかもしれません。
でも、これがハクビシン対策の基本中の基本なんです。
匂いを残さないことが、再侵入を防ぐ鍵になるんです。
洗浄が終わったら、しっかり乾かすことも忘れずに。
湿気が残っていると、カビの原因になっちゃいます。
そうなると、今度はカビの匂いにハクビシンが寄ってくるかもしれません。
- ゴミや落ち葉の除去
- 中性洗剤を使った丁寧な洗浄
- ブラシでのゴシゴシ洗い
- しっかりとした乾燥
でも、「これで匂いが消えて、ハクビシンが寄ってこなくなるんだ!」って思えば、やる気も出てきますよね。
がんばって丁寧に掃除しましょう。
この下準備が、これからの封鎖作業の成功を左右するんです。
金網の取り付け方!「折り返し」と「固定」がポイント
金網の取り付け方、実はコツがあるんです。ポイントは「折り返し」と「固定」。
この二つをしっかりやれば、ハクビシンの侵入をガッチリ防げます。
まず、金網を選ぶときのポイント。
ステンレス製で、目の細かいもの(1センチ以下)を選ぶことが大切です。
ハクビシンは歯が鋭いので、普通の金網だと噛み切られちゃうかもしれません。
さて、いよいよ取り付けです。
まず、金網を侵入口よりも大きめにカットします。
「えっ、大きすぎない?」って思うかもしれませんが、これには理由があるんです。
次に、金網の端を5センチ以上折り返します。
これが「折り返し」のポイントです。
折り返すことで、金網の強度がグッと上がるんです。
「ガシッ」という感じで、しっかりした感じになりますよ。
そして、この折り返した金網を、侵入口にピッタリとあてがいます。
ここからが「固定」のポイント。
ステープルやネジで、しっかりと固定していきます。
- 金網の選び方:ステンレス製、目開き1センチ以下
- 金網のカット:侵入口より大きめに
- 端の折り返し:5センチ以上
- 固定方法:ステープルやネジでしっかりと
大丈夫、これでかなりの効果があります。
ただし、金網だけじゃまだ完璧じゃありません。
次のステップ、シーリング材の使い方も重要なんです。
金網の取り付け、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。
でも、コツさえつかめば、そんなに難しくありません。
「よし、やってみよう!」という気持ちで挑戦してみてください。
ハクビシン対策の大きな一歩になりますよ。
シーリング材の塗り方!「深さ」と「平滑さ」がカギ
シーリング材の塗り方、実は奥が深いんです。ポイントは「深さ」と「平滑さ」。
この二つをマスターすれば、ハクビシンの侵入を完璧に防げます。
まず、シーリング材を選ぶときのコツ。
耐候性と耐久性に優れたものを選ぶことが大切です。
外部用のシリコーン系やポリウレタン系がおすすめです。
「えっ、普通のやつじゃダメなの?」って思うかもしれませんが、長持ちさせるためには適切な選択が必要なんです。
さて、いよいよ塗り方です。
まず、ガンにシーリング材をセットします。
そして、隙間にノズルを深く挿入します。
ここが「深さ」のポイントです。
「グイッ」と奥まで押し込むイメージです。
次に、ゆっくりとガンを引きながら、シーリング材を押し出していきます。
このとき、隙間の奥までしっかりと充填することが大切です。
「ムニュムニュ」とシーリング材が隙間を埋めていく感覚を味わってください。
充填が終わったら、ヘラを使って表面を平らに整えます。
これが「平滑さ」のポイントです。
表面がデコボコしていると、そこから水が入り込んで劣化の原因になってしまいます。
「スーッ」とヘラを滑らせて、きれいに仕上げましょう。
- シーリング材の選び方:耐候性・耐久性のあるもの
- ノズルの挿入:隙間の奥まで深く
- 充填方法:ゆっくりと隙間を埋める
- 表面の仕上げ:ヘラで平らに整える
でも、この丁寧さが長持ちの秘訣なんです。
しっかりと塗ることで、何年も効果が持続するんです。
シーリング材の塗り方、最初は難しく感じるかもしれません。
でも、コツをつかめば意外と簡単です。
「よし、プロみたいに塗ってやろう!」という気持ちで挑戦してみてください。
きっと満足のいく仕上がりになりますよ。
乾燥時間を守れ!完全硬化で耐久性アップ
シーリング材を塗ったら、次は乾燥時間がとっても大切です。ここをしっかり守ることで、封鎖の耐久性がグッとアップします。
「えっ、塗ったら終わりじゃないの?」って思った方、要注意です。
実は、乾燥時間を守らないと、せっかくの作業が台無しになっちゃうんです。
まず、シーリング材の表面が乾くまでの時間。
これは大体2〜3時間くらいです。
この間は絶対に触らないようにしましょう。
「ちょっと触ってみよう」なんて思っても、グッとこらえてくださいね。
指紋がついちゃったら、せっかくの平滑な表面が台無しです。
でも、表面が乾いたからって安心しちゃダメ。
完全に硬化するまでには、24時間以上かかるんです。
この間に雨が降ったり、ハクビシンが接触したりすると、せっかくの封鎖が不完全になっちゃいます。
「そんなに待つの?」って焦るかもしれませんが、ここは忍耐のしどころです。
完全硬化を待つことで、シーリング材の性能が最大限に発揮されるんです。
- 表面乾燥:2〜3時間
- 完全硬化:24時間以上
- 硬化中の注意点:雨や接触を避ける
- 硬化後の確認:触って固さをチェック
もし可能なら、一時的に別の対策(例えば音や光で追い払うなど)を取るのもいいかもしれません。
「待つのはつまらない」なんて思うかもしれません。
でも、この待ち時間が、長期的な効果を生むんです。
「よし、じっくり待とう!」という気持ちで、乾燥時間をしっかり守りましょう。
その先には、ハクビシンの心配のない暮らしが待っているんです。
封鎖後の点検!定期的なチェックで再侵入を防止
封鎖作業が終わっても、油断は大敵です。定期的な点検が、ハクビシン対策の仕上げとなります。
こまめなチェックで、再侵入をしっかり防ぎましょう。
「えっ、もう終わったんじゃないの?」って思う方もいるかもしれません。
でも、家はじっとしているわけじゃありません。
時間とともに、少しずつ変化していくんです。
その変化を見逃さないことが大切なんです。
まず、点検の頻度について。
最初の1か月は週に1回、その後は月に1回程度のチェックがおすすめです。
「そんなにやる必要ある?」って思うかもしれませんが、初期のうちは特に注意が必要なんです。
点検のポイントは主に3つ。
金網の緩み、シーリング材の劣化、新たな噛み跡です。
金網がユルユルになっていないか、シーリング材にヒビが入っていないか、新しい傷跡はないか。
「シッカリ」「ジッー」「キョロキョロ」とチェックしていきましょう。
特に注意が必要なのは、春と秋。
これはハクビシンの繁殖期にあたるんです。
この時期は、彼らが新しい住処を探して活発に動き回ります。
だから、繁殖期前後は特に念入りにチェックする必要があります。
- 点検頻度:初月は週1回、その後は月1回
- チェックポイント:金網の緩み、シーリング材の劣化、新たな噛み跡
- 特に注意する時期:春と秋(繁殖期)
- 異常を見つけたら:すぐに補修を行う
でも、この定期点検が、ハクビシン対策の成功を左右するんです。
小さな変化を見逃さず、すぐに対処することで、大きな被害を防げるんです。
点検作業、最初は慣れないかもしれません。
でも、回数を重ねるうちに、「ここをチェックすればいいんだな」ってコツがつかめてきますよ。
「よし、完璧に点検してやろう!」という気持ちで、定期的なチェックを習慣にしてください。
その努力が、ハクビシンのいない快適な暮らしにつながるんです。
封鎖だけじゃない!ハクビシン撃退の裏技集
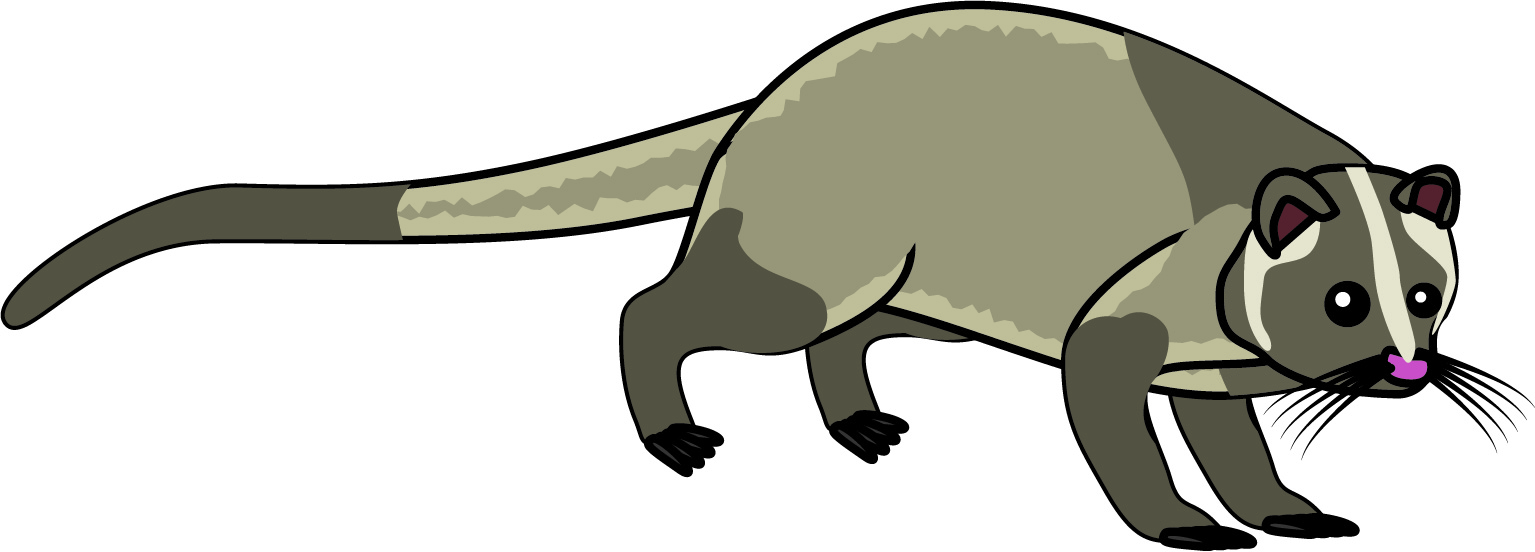
ステンレスたわしが効果的!「歯が引っかかる」仕掛け
ステンレスたわしを使った驚きの対策方法、実はとっても効果的なんです。ハクビシンの歯に引っかかって、侵入を諦めさせる仕掛けなんですよ。
「えっ、台所で使うアレ?」って思った方も多いはず。
そう、まさにそれです。
ステンレスたわしの独特のゴワゴワした感触が、ハクビシンを寄せ付けないんです。
使い方は簡単。
侵入口に詰め込むだけ。
「ギュウギュウ」っと押し込んでいきます。
ハクビシンがこれを噛もうとしても、歯が引っかかって前に進めません。
「イテテ」って感じで、きっと諦めちゃうんです。
でも、注意点もあります。
ステンレスたわしだけでは完全な封鎖はできないんです。
あくまで補助的な対策として使うのがポイント。
金網やシーリング材と組み合わせて使うのが効果的です。
- 侵入口にぴったりサイズのステンレスたわしを用意
- しっかりと押し込んで隙間なく詰める
- 定期的に点検し、緩んでいたら再度詰め直す
- 他の対策と組み合わせて使用する
でも、意外と侮れないんです。
ハクビシンにとっては、ステンレスたわしは「なんだこれ?」という不快な存在。
その不快感が、侵入を諦めさせる大きな要因になるんです。
ステンレスたわし、台所だけじゃなく、ハクビシン対策にも大活躍。
意外な使い方で、家を守る強い味方になってくれるんです。
猫砂の意外な使い方!「天敵の匂い」でハクビシン撃退
猫砂を使ったハクビシン対策、実は秘密兵器なんです。ハクビシンにとって、猫は天敵。
その匂いを利用して撃退するという、なかなかの策士的方法なんですよ。
「えっ、猫砂ってあの臭いやつ?」って思った方、正解です。
でも、その臭いがミソなんです。
ハクビシンは嗅覚が鋭くて、猫の匂いを嗅ぐとビックリして逃げちゃうんです。
使い方は超簡単。
使用済みの猫砂を侵入口の周りにパラパラと撒くだけ。
「フンフン」とハクビシンが匂いを嗅いで、「ヒェー、猫がいる!」って勘違いして逃げ出すわけです。
でも、注意点もあります。
雨に濡れると効果が薄れちゃうので、屋根のある場所での使用がおすすめ。
それに、定期的に新しいものに交換する必要があります。
- 使用済みの猫砂を準備(新品よりも効果的)
- 侵入口周辺に薄く撒く
- 1週間ほどで新しいものに交換
- 雨に濡れないよう注意
ペットショップで少量だけ購入するのもアリ。
または、猫を飼っている友達にお願いするのも手です。
猫砂、意外な使い方でハクビシン対策の強い味方に。
匂いは確かに強いですが、その強さがハクビシンを撃退する武器になるんです。
家族で「うわ、臭い!」って言いながらも、効果を信じて頑張ってみましょう。
ペパーミントオイルの威力!強い香りで寄せ付けない
ペパーミントオイルがハクビシン対策に大活躍!その強烈な香りで、ハクビシンを寄せ付けません。
まるで魔法のような効果があるんです。
「え?あのスースーするやつ?」そう、まさにそれです。
人間には爽やかな香りでも、ハクビシンにとっては「ウッ」となる強烈な刺激なんです。
その刺激臭が、ハクビシンを遠ざける秘密兵器になるわけです。
使い方は簡単。
布や綿球にペパーミントオイルを数滴たらして、侵入口の近くに置くだけ。
「ポタポタ」と垂らして、「フワッ」と香りが広がるイメージです。
でも、注意点もあります。
ペパーミントオイルは強力なので、使いすぎると人間も「ゲホゲホ」となっちゃうかも。
適量を守ることが大切です。
それに、効果は一時的なので、定期的な補充が必要です。
- 100%天然のペパーミントオイルを選ぶ
- 布や綿球に3〜5滴たらす
- 侵入口や通り道に設置
- 1週間ごとに新しいものに交換
- 雨に濡れない場所に置く
大丈夫、侵入口付近だけに置けば、家の中まで香りが広がることはありません。
ペパーミントオイル、その爽やかな香りがハクビシン対策の強い味方に。
「よーし、これでハクビシンとはお別れだ!」って気持ちで、さっそく試してみましょう。
意外と簡単で効果的な対策方法なんです。
光と音の合わせ技!LEDライトと風鈴で警戒心を刺激
光と音を使った驚きの対策方法、実はハクビシンに効果抜群なんです。LEDライトと風鈴の組み合わせで、ハクビシンの警戒心をビンビンに刺激しちゃいます。
「えっ、そんな簡単なもので?」って思うかもしれません。
でも、これが意外と効くんです。
ハクビシンは光と音に敏感。
突然のピカピカとチリンチリンで、ビックリして逃げちゃうんです。
まず、LEDセンサーライトを侵入口の近くに設置します。
人感センサー付きのものがおすすめ。
ハクビシンが近づくと「パッ」と明るく光って、「うわっ」ってなるわけです。
次に風鈴です。
普通の風鈴でもOKですが、金属製の風鈴がより効果的。
ハクビシンにとって、金属音は特に警戒すべき音なんです。
「チリンチリン」という予期せぬ音に、ビクッとなっちゃうんですね。
- 人感センサー付きLEDライトを準備
- 侵入口の近くにLEDライトを設置
- 金属製の風鈴を用意
- LEDライトの近くに風鈴を吊るす
- 定期的にバッテリーや電池をチェック
大丈夫、LEDライトは侵入口に向けて設置すれば、ご近所さんの迷惑にはなりません。
風鈴も、そよ風で鳴る程度なら問題ないはずです。
この光と音の合わせ技、意外とシンプルですが効果は抜群。
「よし、これでハクビシンともお別れだ!」って気持ちで、ぜひ試してみてください。
ハクビシンにとっては、まさに「お化け屋敷」状態。
きっと近づきたくなくなるはずです。
自然素材で対策!「唐辛子」と「コーヒーかす」の活用法
自然素材を使ったハクビシン対策、実は身近なもので簡単にできちゃうんです。今回の主役は「唐辛子」と「コーヒーかす」。
この二つの組み合わせが、ハクビシンを撃退する強力な武器になるんです。
まず、唐辛子。
「えっ、あの辛いやつ?」そう、まさにそれです。
ハクビシンは辛いものが大の苦手。
唐辛子の刺激的な成分が、ハクビシンを寄せ付けないんです。
使い方は簡単。
唐辛子パウダーを水で溶いて、スプレーボトルに入れるだけ。
これを侵入口周辺に「シュッシュッ」とスプレーします。
ハクビシンが近づくと、「ヒリヒリ」として逃げ出すわけです。
次はコーヒーかす。
「えっ、捨てちゃうアレ?」って思った方、ちょっと待ってください。
実は、このコーヒーかすがハクビシン対策の強い味方になるんです。
コーヒーかすの使い方も超簡単。
乾燥させたコーヒーかすを、侵入口周辺にパラパラと撒くだけ。
強い香りがハクビシンの敏感な鼻を刺激して、「うわっ、この臭い!」って逃げ出すんです。
- 唐辛子スプレーの作り方:
- 唐辛子パウダー大さじ1を水1リットルで溶く
- スプレーボトルに入れて、よく振る
- 侵入口周辺に吹きかける
- コーヒーかすの使い方:
- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる
- 侵入口周辺に薄く撒く
- 1週間ほどで新しいものに交換
確かに、屋外での使用は天候の影響を受けやすいです。
だから、定期的なメンテナンスが大切。
雨が降ったら、また新しく対策をし直す必要があります。
この自然素材を使った対策、効果はバッチリなのに環境にも優しい。
「一石二鳥だな」って感じですよね。
家族みんなで「よし、がんばろう!」って気持ちで、ハクビシン対策に取り組んでみてください。
きっと、ハクビシンとはさよならできるはずです。