ハクビシンが通れる隙間のサイズは?【最小10cm四方】この知識を活かした効果的な侵入防止策


【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの侵入に悩まされていませんか?- ハクビシンが通過可能な最小サイズは約10cm四方
- 子ハクビシンは7〜8cm程度の隙間も通過可能
- 体を平らにすると高さ5cmの隙間も侵入の可能性あり
- 屋根裏や壁の隙間がハクビシンの主な侵入経路
- 季節や時間帯によって侵入パターンが変化
- 身近な道具を使った効果的な対策方法あり
実は、この小さな生き物は驚くほど小さな隙間から家に入り込めるんです。
10cm四方の隙間があれば、大人のハクビシンでも楽々通過。
さらに驚くことに、子どものハクビシンなら7〜8cmの隙間も通れてしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いはず。
でも、ご安心ください。
この記事では、ハクビシンが通れる隙間のサイズと、5つの意外な侵入経路をご紹介します。
これを知れば、効果的な対策が立てられますよ。
さあ、ハクビシン撃退の第一歩を踏み出しましょう!
【もくじ】
ハクビシンが通れる隙間のサイズを知ろう!

ハクビシンが侵入できる最小サイズは「10cm四方」!
ハクビシンが通れる最小の隙間サイズは、なんと10cm四方なんです。これは意外と小さいと思いませんか?
「えっ、そんな小さな隙間から入ってくるの?」そう思った方も多いはず。
でも、実はハクビシンの体は驚くほど柔軟なんです。
頭が通れる隙間なら、体全体を押し込んでしまうという特徴があります。
ハクビシンの体の構造を想像してみてください。
細長い体に、やや平たい頭。
この体型が、小さな隙間を通り抜けるのに適しているんです。
まるでヘビのように体をくねらせて、スルスルっと隙間を通り抜けてしまいます。
では、具体的にどんなものと比べればイメージしやすいでしょうか?
- ペットボトル(2リットル)の底の直径
- CDケースの短辺
- ハガキの短辺
「へえ、こんなに小さいの?」と驚く方も多いかもしれません。
家の中を見回してみると、こんな隙間がいくつも見つかるかもしれません。
換気口、壁の隙間、屋根裏への入り口など、思わぬところに侵入口があるかもしれないのです。
「でも、うちは大丈夫だよ」なんて油断は禁物。
ハクビシンは意外なところから侵入してくる可能性があります。
次は、もっと驚きの事実をお伝えしますよ。
子ハクビシンなら「7〜8cm」の隙間も要注意!
大人のハクビシンでさえ10cm四方の隙間を通れるのに、子ハクビシンならなんと7〜8cmの隙間も通過できてしまうんです。これはもう、ほんの小さな隙間でも侵入の可能性があるということ。
「えっ、そんな小さな隙間から入ってくるの?」と驚く声が聞こえてきそうです。
でも、これが事実なんです。
子ハクビシンの体は、まるでゴムのように柔らかくて、驚くほど小さな隙間を通り抜けることができるんです。
具体的にどのくらいの大きさかイメージできますか?
例えば、こんなものと比べるとわかりやすいかもしれません。
- 単三電池を2本並べた幅
- ティッシュボックスの高さ
- スマートフォンの幅
この大きさの隙間なら、家の中にいくつもありそうですよね。
子ハクビシンが通れる隙間は、成獣より2〜3cm小さいんです。
これは体の大きさの違いだけでなく、骨格がまだ柔らかいことも関係しています。
まるでねずみのように、小さな隙間をするすると通り抜けてしまうんです。
「でも、うちには子どものハクビシンなんていないよ」なんて思っていませんか?
実は、春と秋の年2回、ハクビシンの繁殖期があるんです。
この時期には、子ハクビシンが増える可能性が高くなります。
家の中に7〜8cmの隙間がないか、もう一度よーく確認してみましょう。
特に、壁と床の間や、窓枠の隙間、配管の周りなど、見落としがちな場所に注目です。
小さな隙間も侵入口になる可能性があるんです。
次は、もっと驚きの事実をお伝えしますよ。
ハクビシンは体を平らにして「高さ5cm」の隙間も通過!
驚くべきことに、ハクビシンは体を平らにすることで、なんと高さ5cmの隙間も通過できてしまうんです。「えっ、そんな薄っぺらになれるの?」と驚く声が聞こえてきそうですね。
ハクビシンの体は、まるでパンケーキのように平たくなれるんです。
想像してみてください。
床と天井の間にある5cmの隙間。
普通の動物なら絶対に通れないと思いますよね。
でも、ハクビシンならスイスイと通り抜けてしまうんです。
具体的にどのくらいの高さか、身近なもので例えてみましょう。
- スマートフォンを2台重ねた高さ
- ノートの厚さ
- マグカップの高さの半分くらい
でも、これが事実なんです。
ハクビシンがこんなに体を平らにできる理由は、その柔軟な骨格にあります。
胸郭(肋骨のある部分)が非常に柔軟で、押しつぶすように平たくなることができるんです。
まるでスクイーズ遊びのおもちゃのように、ぺちゃんこになれるわけです。
この能力は、ハクビシンの生存戦略の一つです。
狭い場所に隠れたり、小さな隙間から餌のある場所に侵入したりするのに役立っています。
自然界では素晴らしい能力ですが、私たちの家にとっては大きな脅威になるんです。
「うちの家にそんな隙間はないよ」なんて思っていませんか?
でも、意外なところに5cmの隙間が隠れているかもしれません。
例えば、エアコンの配管が通る穴、古い建物の床下の隙間、屋根裏への入り口など。
これらの場所を再確認してみる必要がありそうです。
ハクビシンの驚くべき能力を知ったところで、次は具体的な対策を考えていきましょう。
10cm未満でも侵入の可能性あり!個体差に注意
10cm未満の隙間でも、ハクビシンが侵入してくる可能性があるんです。「えっ、それじゃあどうすればいいの?」と不安になる方もいるでしょう。
でも、大丈夫。
知識があれば対策も立てられます。
ハクビシンの体の大きさには個体差があります。
小柄な個体なら、9cm程度の隙間でも通れてしまうことがあるんです。
まるで、人間の中にも背の高い人や低い人がいるのと同じですね。
では、どんなところに注意すればいいのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
- 換気口や排水口の周り
- 屋根と壁の接合部
- 古い建物の床下や壁の隙間
- 窓や戸の隙間
- 配管やケーブルの通り道
「うちは大丈夫」と思っていても、意外な隙間が見つかるかもしれません。
個体差による侵入リスクを考えると、「じゃあ、全ての隙間を完全に塞げばいいんでしょ?」と思うかもしれません。
でも、それは現実的ではありません。
家にはある程度の換気や排水が必要だからです。
そこで、重要になってくるのが「バランス」です。
必要な開口部は残しつつ、ハクビシンが通れそうな隙間は徹底的に塞ぐ。
そんな対策が求められます。
例えば、換気口には細かい金網を取り付ける。
排水口には蓋をする。
屋根と壁の隙間にはコーキング材を詰める。
こういった対策を組み合わせることで、ハクビシンの侵入を防ぎつつ、家の機能も保つことができるんです。
「でも、そんなの面倒くさい…」なんて思わないでくださいね。
ハクビシンが家に入り込んでしまったら、もっと大変なことになるんです。
糞尿による衛生問題、電線をかじることによる火災リスク、騒音問題など、様々なトラブルの元になってしまいます。
個体差を考慮した対策を立てることで、より安全で快適な住環境を作ることができます。
小さな努力が、大きな安心につながるんです。
隙間を放置するのは逆効果!早めの対策が重要
小さな隙間を放置しておくのは、実はとっても危険なんです。「えっ、そんな小さな隙間くらい…」なんて思っていませんか?
でも、それが大きな問題につながる可能性があるんです。
ハクビシンは、小さな隙間を見つけると、そこを広げようとする習性があります。
まるで、子どもがおもちゃの穴を広げて遊ぶように、ハクビシンも隙間を少しずつ大きくしていくんです。
例えば、こんな事態が起こり得ます。
- 換気口の周りをかじって穴を広げる
- 屋根裏の小さな隙間を爪でひっかいて拡大する
- 壁の中の配線を引っ張り出して穴を作る
でも、これが彼らの自然な行動なんです。
小さな隙間を放置しておくと、時間とともに問題が大きくなっていきます。
最初は入れなかった隙間も、ハクビシンの努力(?
)によって、いつの間にか立派な侵入口になってしまうんです。
さらに悪いことに、一度ハクビシンが入り込んでしまうと、そこが彼らのお気に入りスポットになってしまう可能性があります。
「ここは快適だな」と思ったハクビシンは、どんどん仲間を呼んでくるかもしれません。
そうなると、被害はさらに拡大してしまいます。
だからこそ、早めの対策が重要なんです。
小さな隙間を見つけたら、すぐに対処することが大切です。
「面倒くさいな」なんて後回しにしていると、取り返しのつかないことになりかねません。
具体的な対策方法としては、以下のようなものがあります。
- 金属製のメッシュで隙間を塞ぐ
- 隙間にコーキング材を詰める
- 専用の侵入防止グッズを使用する
小さな隙間も侮れません。
「備えあれば憂いなし」ということわざがありますが、まさにその通りです。
早めの対策が、安心して暮らせる家を作る第一歩になるんです。
ハクビシンの侵入経路を特定し効果的に対策しよう
屋根裏vs壁の隙間!ハクビシンが好む侵入口
ハクビシンが最も好む侵入口は、なんと屋根裏と壁の隙間なんです。「えっ、そんなところから入ってくるの?」と驚く方も多いはず。
屋根裏は、ハクビシンにとって理想的な住処なんです。
暗くて暖かく、人の目も届きにくい。
まるで高級マンションのペントハウスのような快適空間です。
一方、壁の隙間は、ハクビシンにとっては便利な抜け道。
家の中と外を自由に行き来できる秘密の通路みたいなものです。
では、具体的にどんなところに注意すればいいのでしょうか?
- 屋根と壁の接合部の隙間
- 軒下や破損した屋根瓦の隙間
- 外壁の亀裂や破損箇所
- 古い建物の木部が腐った箇所
「うちは大丈夫」なんて油断は禁物。
ハクビシンは意外なところから侵入してくる可能性があります。
特に注意が必要なのは、古い家屋です。
年月が経つにつれて、建物にはどうしても隙間ができやすくなります。
まるで、人間の歯に虫歯ができるようなものです。
そして、その小さな隙間をハクビシンは見逃しません。
「でも、うちは新築だから大丈夫でしょ?」なんて思っていませんか?
実は、新築家屋でも油断は禁物なんです。
建築時の小さなミスや、材料の収縮などで思わぬ隙間ができることがあります。
定期的なチェックが大切です。
特に、台風や大雨の後は要注意。
建物にダメージが出て、新たな隙間ができている可能性があります。
家の周りをぐるっと一周して、suspicious(怪しい)な箇所がないかチェックしてみましょう。
換気口と排水管の違い!ハクビシンの侵入リスク比較
換気口と排水管、どちらがハクビシンの侵入リスクが高いか知っていますか?実は、圧倒的に換気口の方が危険なんです。
換気口は、ハクビシンにとって格好の侵入口。
なぜなら、換気口は直接家の中につながっているからです。
まるで、家の中へのエクスプレス切符のようなもの。
一方、排水管は少し事情が異なります。
排水管は確かに家につながっていますが、ハクビシンが通るには少々難しい構造になっています。
曲がりくねった配管や、水がたまっている部分があるため、ハクビシンにとっては難関コースのようなものです。
では、具体的にどんなところに注意すればいいのでしょうか?
- 屋根や壁面の換気口
- エアコンの室外機周りの隙間
- 台所や浴室の換気扇
- 屋根裏や床下の換気口
「うちの換気口は小さいから大丈夫」なんて思っていませんか?
でも、ハクビシンは意外と小さな隙間から入り込めるんです。
特に注意が必要なのは、網のない換気口です。
網がないと、ハクビシンにとってはまるで「いらっしゃいませ」と書いた看板を出しているようなものです。
一方、排水管はどうでしょうか?
確かに、排水管からハクビシンが侵入することもゼロではありません。
でも、その可能性は換気口に比べるとぐっと低くなります。
ただし、屋根の雨どいには注意が必要です。
これは排水管の一種ですが、ハクビシンが登って屋根に到達する足場になることがあります。
「じゃあ、換気口を全部塞いじゃえばいいんでしょ?」なんて思わないでくださいね。
換気は家にとって重要な機能です。
代わりに、細かい網を取り付けるなどの対策を取りましょう。
これで、新鮮な空気は取り入れつつ、ハクビシンはシャットアウトできるんです。
冬と夏で変化!季節別のハクビシン対策ポイント
ハクビシンの行動は季節によってがらりと変わるんです。「えっ、動物なのに季節で変わるの?」と思う方もいるかもしれませんね。
でも、これが事実なんです。
まず、冬のハクビシン。
寒さをしのぐために、暖かい場所を必死で探します。
家の中、特に屋根裏や壁の中は、ハクビシンにとって理想的な冬の住処なんです。
まるで、私たちが寒い日にこたつに潜り込むようなものですね。
一方、夏のハクビシン。
暑さを避けるために、涼しい場所を探し回ります。
家の中の風通しの良い場所や、エアコンの効いた空間を好みます。
ちょうど、私たちが暑い日に木陰を探すようなイメージです。
では、季節別の対策ポイントを見ていきましょう。
冬の対策:
- 屋根裏や壁の隙間を徹底的にチェック
- 暖房の排気口周りを重点的に防御
- 家の周りの落ち葉や枯れ枝を片付ける(隠れ場所になるため)
- 換気口や窓の網戸の点検と補強
- エアコンの室外機周りの隙間をふさぐ
- 庭の果樹や野菜の収穫をこまめに行う(餌を減らす)
季節に合わせた対策をすることで、より効果的にハクビシンを撃退できるんです。
特に注意が必要なのは、季節の変わり目です。
ハクビシンが新しい住処を探し始める時期なので、家の周りを歩き回る姿を見かけることが増えます。
この時期こそ、しっかりと対策を立てましょう。
また、繁殖期である春と秋も要注意です。
子育てのために、より安全で快適な場所を探すハクビシンが増えます。
「我が家は子育てには向いていません」とアピールするために、忌避剤を使うのも良いでしょう。
季節の変化を味方につけて、ハクビシン対策を効果的に行いましょう。
こうすれば、一年中安心して暮らせる家になりますよ。
昼と夜の侵入パターンの差!24時間警戒が必要
ハクビシンの侵入パターンは、昼と夜でまるで違うんです。「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いはず。
でも、これが事実なんです。
まず、夜のハクビシン。
夜9時から深夜2時頃がもっとも活発になります。
まるで、夜型人間のように夜になると元気いっぱい。
この時間帯、ハクビシンは食べ物を探して家の周りをうろうろしたり、新しい住処を探したりしているんです。
一方、昼のハクビシン。
基本的には昼間は休んでいますが、完全に活動しないわけではありません。
特に、餌が不足している時期や子育て中は昼間も活動することがあります。
ちょうど、私たちが夜中にお腹が空いて冷蔵庫を漁るようなものですね。
では、時間帯別の対策ポイントを見ていきましょう。
夜の対策:
- センサーライトの設置(明るい場所は苦手)
- 音の出る装置の設置(突然の音にびっくり)
- 食べ物やゴミの適切な管理(誘引物を減らす)
- 定期的な見回り(異常がないかチェック)
- 換気口や隙間の点検(侵入口の確認)
- 庭の整備(隠れ場所をなくす)
全ての時間帯でピリピリする必要はありません。
それぞれの時間帯に合わせた対策を立てることで、効率的に防御できるんです。
特に注意が必要なのは、夕方から夜にかけての時間帯です。
ハクビシンが活動を始める時間なので、この時間帯に食べ物やゴミを外に放置するのは避けましょう。
まるで、ハクビシンに「いらっしゃい」と言っているようなものです。
また、早朝も要注意です。
夜通し活動していたハクビシンが、日の出前に隠れ場所を探すかもしれません。
この時間帯に換気口や隙間をチェックするのが効果的です。
時間帯によって変わるハクビシンの行動を理解し、それに合わせた対策を立てることが大切です。
こうすれば、24時間安心できる家づくりができますよ。
木造住宅と鉄筋コンクリート!建物別の弱点
建物の種類によって、ハクビシンの侵入しやすさは全然違うんです。「えっ、建物の種類で変わるの?」と思う方も多いはず。
でも、これが重要なポイントなんです。
まず、木造住宅。
ハクビシンにとっては侵入しやすい構造です。
なぜなら、木材は年月とともに劣化し、隙間ができやすいからです。
まるで、古いセーターに穴が開くようなものですね。
特に注意が必要なのは以下の部分です。
- 屋根裏への侵入口
- 外壁の隙間
- 基礎と土台の間の隙間
- 雨樋や軒下の隙間
木造に比べると侵入しにくい構造です。
コンクリートは硬くて丈夫なので、ハクビシンが爪で引っかいても簡単には穴が開きません。
でも、油断は禁物。
次の部分には注意が必要です。
- 換気口や通気口
- 配管やケーブルの貫通部
- ベランダや屋上への侵入経路
- 外壁のひび割れ
建物の種類に関わらず、適切な対策は必要です。
木造住宅の対策ポイントは、定期的なメンテナンスです。
特に雨漏りには要注意。
雨漏りは木材を腐らせ、ハクビシンの格好の侵入口を作ってしまいます。
また、外壁の塗り替えや屋根の点検も大切です。
鉄筋コンクリート造の対策ポイントは、開口部の管理です。
換気口や通気口には細かい網を取り付け、配管やケーブルの貫通部はしっかりとふさぎましょう。
また、外壁のひび割れは早めに補修することが大切です。
建物の種類によって弱点が違うことを理解し、それぞれに合った対策を立てることが重要です。
こうすれば、どんな建物でもハクビシン対策はバッチリ。
安心して暮らせる家になりますよ。
ハクビシン撃退!効果的な対策と驚きの裏技
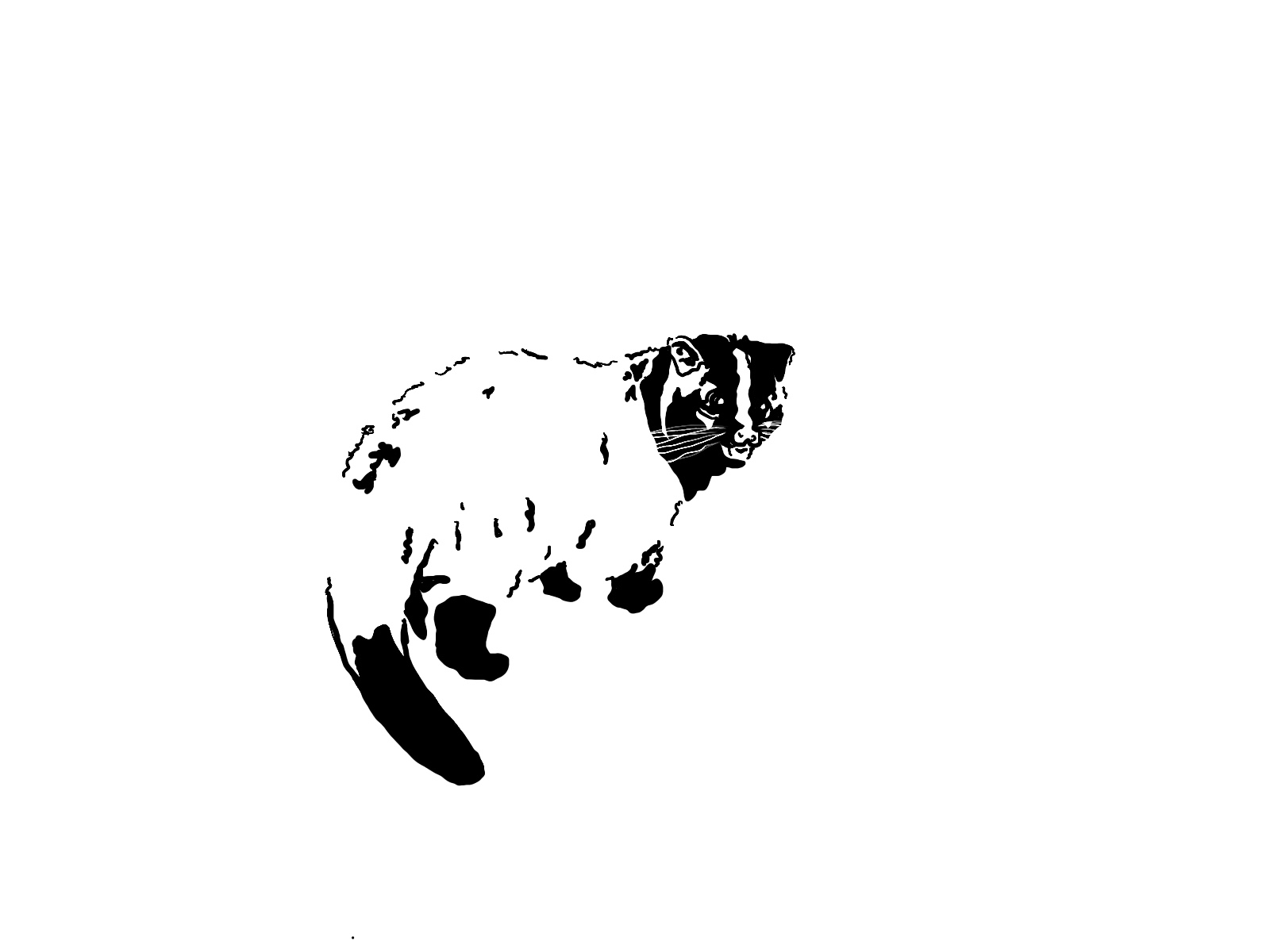
ペットボトルで簡単!手作りサイズチェッカーの作り方
ペットボトルを使って、ハクビシンが通れる隙間サイズを簡単にチェックできるんです。これは本当に便利な裏技ですよ。
「えっ、ペットボトルでそんなことができるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
ペットボトルを利用して、10cm四方のサイズチェッカーを作ることができます。
作り方はとってもカンタン。
まず、2リットルのペットボトルを用意します。
底の部分を切り取って、高さ10cmほどの円筒形を作ります。
これで完成です。
このサイズチェッカーを使って、家の周りの隙間をチェックしていきましょう。
- 屋根と壁の接合部
- 換気口の周り
- 配管の通り道
- 窓やドアの隙間
ハクビシンが侵入できる可能性が高いということです。
「うわっ、こんなところにも隙間が!」なんて驚くかもしれません。
でも、心配しないでください。
見つけた隙間は、すぐに対策を立てましょう。
金網や板で塞ぐなど、適切な方法で対処することが大切です。
このペットボトルサイズチェッカー、実は子供と一緒に作るのも楽しいんです。
まるで宝探しゲームのように、家の周りの隙間を探すことができます。
「あっ、ここに隙間があった!」なんて声が聞こえてくるかも。
家族みんなでハクビシン対策、楽しみながらできちゃいます。
安全性と楽しさを兼ね備えた、まさに一石二鳥の方法なんです。
さあ、今すぐペットボトルを手に取って、隙間チェックを始めましょう!
LEDテープライトの活用法!暗闇の隙間を可視化
暗闇に潜む隙間を見つけるのに、LEDテープライトが大活躍するんです。これって、まるで探偵の秘密道具みたい!
「えっ、LEDテープライトでそんなことができるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
LEDテープライトを使うと、目に見えにくい小さな隙間も鮮やかに浮かび上がるんです。
使い方はとってもシンプル。
夜になったら、LEDテープライトを持って家の外を歩き回ります。
家の壁に沿ってゆっくりとライトを動かしていくんです。
すると…
- 壁と屋根の接合部の隙間
- 窓枠周りのわずかな隙き間
- 外壁の小さなひび割れ
- 配管周りの見えにくい隙間
「わっ、こんなところに隙間があったの?」なんて驚くことばかり。
LEDテープライトの光が隙間を通り抜けると、家の中から光が漏れて見えます。
これが隙間の目印になるわけです。
まるで、暗闇に浮かぶ星座のよう。
でも、ただ見つけるだけじゃダメ。
見つけた隙間はしっかりメモを取りましょう。
「ここに2mm幅の隙間あり」なんて具合に。
後で、この情報を元に適切な対策を立てるんです。
この方法、実は友達や家族と一緒にやるとより効果的。
「あっ、ここ光ってる!」「えっ、本当だ!」なんてやり取りをしながら、楽しく隙間探しができちゃいます。
LEDテープライトを使った隙間チェック、夜の家族の新しい楽しみになるかもしれませんね。
さあ、今夜からLEDテープライトを手に、ハクビシン対策の夜回りを始めましょう!
風船テクニックで隙間発見!空気の流れを利用
風船を使って隙間を見つける方法があるんです。これって、まるで魔法みたい!
「えっ、風船で隙間が分かるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
風船を使うと、目に見えない空気の流れを感じ取れるんです。
やり方はこんな感じ。
まず、風船を膨らませます。
そして、家の中を歩き回りながら、風船を壁や窓、ドアの近くでゆっくり動かします。
すると…
- 窓枠からの微かな風
- ドア下の隙間からの空気の流れ
- 壁のひび割れからのそよ風
- 床と壁の間の空気の動き
「あれ?ここで風船がピクッと動いた!」なんて発見があるかもしれません。
風船が動く仕組みは簡単。
隙間から入ってくる外気が風船を押すんです。
小さな隙間でも、空気は通りますからね。
まるで、風船が「ここだよ!」って教えてくれているみたい。
見つけた隙間は、すぐにメモしておきましょう。
「北側の窓、右下に空気の流れあり」なんて具合に。
この情報を元に、後でしっかり対策を立てるんです。
この方法、子供と一緒にやるととっても楽しいんですよ。
「お父さん、風船が動いたよ!」「本当だね。ここに隙間があるみたいだ」なんてやり取りしながら、家族で楽しく隙間探しができちゃいます。
風船テクニックを使った隙間チェック、家族の新しい週末の楽しみになるかもしれませんね。
さあ、今すぐ風船を膨らませて、ハクビシン対策の隙間探しを始めましょう!
ドライアイスの煙で侵入経路特定!意外な使い方
ドライアイスの煙を使って、ハクビシンの侵入経路を見つける方法があるんです。これって、まるで科学マジックショーみたい!
「えっ、ドライアイスでそんなことができるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これがとっても効果的なんです。
ドライアイスの煙を使うと、目に見えない隙間からの空気の流れがはっきりと分かるんです。
やり方はこんな感じ。
まず、ドライアイスを用意します。
注意:ドライアイスは直接触らないでくださいね。
それを大きめの容器に入れて、少量のお湯を加えます。
すると、モクモクと白い煙が出てきます。
この煙を使って…
- 壁際や床との境目
- 窓やドアの周り
- 配管やケーブルの通り道
- 換気口や通気口
すると、隙間がある場所では煙が吸い込まれたり、逆に外から中に入ってきたりするのが見えます。
「わっ、煙が消えた!」「あっ、こっちから煙が出てきた!」なんて驚きの連続です。
この方法のすごいところは、目に見えない小さな隙間も見つけられること。
煙は空気よりも重いので、床に近い隙間も見逃しません。
まるで、煙が探偵になって隙間を教えてくれているみたい。
見つけた隙間は必ずメモしておきましょう。
「玄関ドア下部、煙の流出あり」なんて感じで。
この情報を元に、しっかりとした対策を立てるんです。
この方法、大人の監督のもとで子供と一緒にやるととても楽しいですよ。
「お母さん、煙が動いたよ!」「本当だね。ここに隙間があるみたいだよ」なんて会話しながら、家族で楽しく隙間探しができちゃいます。
ドライアイスの煙を使った隙間チェック、家族の新しい冒険になるかもしれませんね。
さあ、準備ができたら、科学マジックショーのようなハクビシン対策を始めましょう!
タルク粉で足跡を可視化!ハクビシンの動線を追跡
タルク粉を使って、ハクビシンの足跡を見つける方法があるんです。これって、まるで探偵ドラマの捜査テクニックみたい!
「えっ、タルク粉でそんなことができるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これがとってもよく効くんです。
タルク粉を使うと、目に見えないハクビシンの足跡がくっきりと浮かび上がるんです。
やり方はこんな感じ。
まず、ハクビシンが通りそうな場所にタルク粉を薄く撒きます。
例えば…
- 庭と家の境目
- 物置の周り
- ゴミ置き場の近く
- 果樹や野菜畑の入り口
そして、翌朝確認してみましょう。
もしハクビシンが通ったなら、タルク粉の上にくっきりと足跡が残っているはずです。
「わっ、本当に足跡がある!」「こんな所を通ってたんだ!」なんて驚きの発見があるかもしれません。
この方法のすごいところは、ハクビシンの動線が分かること。
どこから侵入して、どこを通って、どこへ向かったのか。
まるで、ハクビシンの行動日記を読んでいるみたい。
見つけた足跡は必ず写真に撮っておきましょう。
「南側の庭、物置に向かう足跡あり」なんて感じでメモも残しておくといいですね。
この情報を元に、的確な対策を立てることができるんです。
この方法、子供と一緒にやるととてもわくわくしますよ。
「お父さん、足跡見つけたよ!」「すごいね。どんな形をしてる?」なんて会話しながら、家族で楽しく証拠探しができちゃいます。
タルク粉を使った足跡チェック、家族の新しい朝の日課になるかもしれませんね。
さあ、タルク粉を準備して、ハクビシン探偵団の活動を始めましょう!