ハクビシンからりんごを守るには?【収穫直前が最も危険】効果的な5つの樹木保護策を紹介

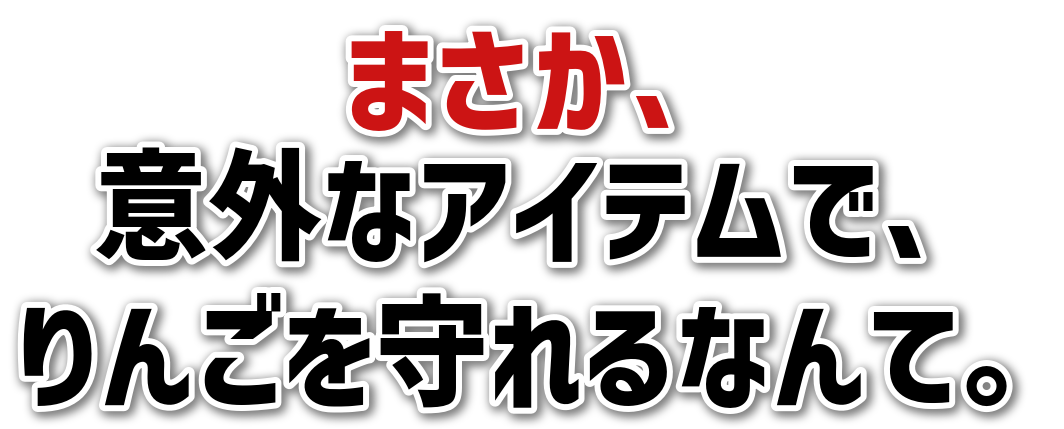
【この記事に書かれてあること】
りんご園を守る戦いが始まります!- ハクビシンは収穫直前のりんごを特に狙う傾向がある
- 落下果実の放置がハクビシンを引き寄せる大きな要因に
- ネットや金属ガードなどの物理的な防御策が最も効果的
- 忌避剤は一時的な効果しかないため、継続的な対策が必要
- 意外なアイテムを活用した驚きの裏技で被害を激減させられる
ハクビシンの被害に悩まされているあなたに、驚きの裏技をお届けします。
実は、収穫直前のりんごが最も危険なんです。
でも、大丈夫。
ネットや金属ガードといった定番の対策から、ラベンダーやLEDライトを使った意外な方法まで、効果的な対策を5つご紹介します。
これらの方法で、ハクビシンの被害を激減させ、美味しいりんごを守り抜きましょう。
あなたのりんご園が、再び豊かな実りに包まれる日はすぐそこです!
【もくじ】
ハクビシンがりんごを狙う理由と被害の実態

収穫直前のりんごが「最も危険」な理由とは!
収穫直前のりんごは、甘い香りと柔らかい実が最も充実する時期です。そのため、ハクビシンにとって最高の食事となるのです。
ハクビシンは優れた嗅覚の持ち主。
収穫直前のりんごが放つ甘い香りは、彼らにとって「こんにちは、美味しいごはんですよ〜」と呼びかけているようなものです。
この時期のりんごは糖度が最も高く、果肉も柔らかくなっているため、ハクビシンにとっては食べやすく、栄養価も高い理想的な食べ物なんです。
さらに、収穫直前のりんごは木に長くとどまっているため、ハクビシンが見つけやすく、食べる機会も増えてしまいます。
「せっかく大切に育てたりんごなのに…」と思う気持ちもわかります。
でも、ここで諦めてはいけません!
対策としては、以下のようなものがあります。
- 収穫時期を少し早めに設定する
- 木全体を細かい網で覆う
- 夜間にライトを設置して警戒する
- 収穫直前は見回りの頻度を増やす
大切なりんごを守るため、収穫直前こそ気を抜かずに対策を講じましょう。
ハクビシンの被害パターン「食べ方」に要注意
ハクビシンのりんごの食べ方は、まるで美食家のよう。完熟したりんごを丸かじりし、果肉を食べ尽くして種子だけを残すのが特徴です。
「えっ、そんなに上品に食べるの?」と思われるかもしれません。
でも、これが厄介なんです。
ハクビシンは木に登って、最も甘くて美味しいりんごを選んで食べるため、農家さんにとっては大切な商品価値の高いりんごが狙われてしまうのです。
ハクビシンの食べ方の特徴をもう少し詳しく見てみましょう。
- 鋭い爪と歯で、りんごの皮をきれいに剥く
- 果肉を少しずつ丁寧に食べていく
- 種子の周りまできれいに食べ尽くす
- 種子は残して、次のりんごに移動
- 一晩で複数のりんごを食べ荒らす
- 半分だけ食べられたりんごが多数見つかる
- 木の上の方にある、よく熟したりんごから食べられる
- かじり跡がきれいで、人間が食べたようにも見える
確かにその通りなんです。
でも、ハクビシンにとっては自然な行動なんですね。
対策としては、木全体を覆うネットを設置したり、収穫をこまめに行ったりするのが効果的です。
ハクビシンの食べ方を知ることで、より効果的な対策を立てることができるんです。
りんごを守るためには、敵を知ることが大切なんですね。
りんごvs他の果物!ハクビシンが好む順位は
ハクビシンは果物好きの食いしん坊さん。でも、全ての果物が同じように好きというわけではありません。
実は、ハクビシンにはお気に入りの果物ランキングがあるんです。
そのランキングのトップに君臨しているのが、なんとりんごなんです!
「えっ、りんごがナンバーワン?」と驚かれるかもしれません。
でも、理由があるんです。
りんごがハクビシンに人気の理由は以下の通りです。
- 甘くて香り豊か
- 栄養価が高い
- 木になっている期間が長い
- 皮が柔らかく食べやすい
ハクビシンの好み順に並べるとこんな感じです。
- りんご
- 柿
- 桃
- 梨
- ぶどう
例えば、梨はりんごと同じリンゴ科の果物ですが、ハクビシンの好み順位では下位になっています。
これは、梨の皮が硬くて食べにくいことや、木になっている期間が比較的短いことが関係しているんです。
一方で、柿が2位なのは興味深いですね。
柿は甘くて柔らかく、栄養価も高いため、ハクビシンにとっては魅力的な果物なんです。
この好み順位を知ることで、果樹園全体の防衛戦略を立てることができます。
例えば、りんごの木により重点的に対策を施したり、ハクビシンの好みが低い果物を外周に植えたりするのも一つの手です。
「ハクビシンめ、よくもうちのりんごを…!」と怒りたくなる気持ちはわかります。
でも、彼らにとってはりんごが最高のごちそうなんです。
この事実を踏まえて、より効果的な対策を考えていきましょう。
ハクビシンの侵入経路「意外な場所」に注目
ハクビシンは驚くほど器用で、思いもよらない場所から侵入してくることがあります。「えっ、そんな所から入ってくるの?」と驚くような経路もあるんです。
まず、ハクビシンの一般的な侵入経路をおさらいしましょう。
- 木の枝を伝って侵入
- フェンスや壁を登って侵入
- 地面から直接りんご園に侵入
ハクビシンは意外な場所からも侵入してくるんです。
その「意外な場所」とは…
- 排水パイプや雨どい
- 電線や電柱
- 隣接する建物の屋根
- 果樹園の看板や支柱
- 風で倒れた木や積み上げた資材
でも、ハクビシンは非常に賢く、体も柔軟なんです。
彼らにとっては、これらの「意外な場所」も立派な侵入経路になってしまうんです。
特に注意が必要なのは、排水パイプや雨どいです。
ハクビシンはこれらを「高速道路」のように使って、あっという間に果樹園の中心部まで侵入してしまいます。
「ズルズル…ガサガサ…」という音が夜中に聞こえたら、要注意です。
対策としては、これらの意外な侵入経路にも目を向けることが大切です。
例えば、
- 排水パイプの周りに滑りやすい素材を巻く
- 電線にトゲのあるカバーを取り付ける
- 看板や支柱の周りに金属製のガードを設置する
「ハクビシンって、こんなに頭がいいんだ…」と感心してしまうかもしれません。
でも、彼らの賢さを理解することで、より効果的な対策が立てられるんです。
意外な侵入経路にも目を光らせて、大切なりんごを守りましょう。
効果的なりんごの木の保護方法と落下果実対策
ネットvs金属ガード!どちらが効果的か
結論から言うと、ネットと金属ガードの両方を組み合わせるのが最も効果的です。でも、どちらか一つを選ぶなら、ネットの方がおすすめです。
「えっ、そんなに違うの?」と思われるかもしれません。
実は、ネットと金属ガードには、それぞれ長所と短所があるんです。
まず、ネットの良いところを見てみましょう。
- 木全体を覆えるので、高い場所のりんごも守れる
- 軽くて扱いやすい
- 比較的安価
- 鳥による被害も防げる
- 丈夫で長持ち
- ハクビシンが噛み切れない
- 見た目がすっきりしている
でも、ちょっと待ってください。
金属ガードには大きな弱点があるんです。
それは、高さが限られているということ。
通常、金属ガードは地面から60cmほどの高さまでしか設置できません。
つまり、それより上の部分は無防備になってしまうんです。
ハクビシンは木登りが得意で、2〜3mの高さまで簡単に登れます。
「えいっ」と軽々と金属ガードを飛び越えて、おいしいりんごにありつけちゃうんです。
だからこそ、木全体を覆えるネットの方が効果的なんです。
目合いが4cm以下の細かいネットを選んで、地面までしっかり覆いましょう。
「ガサガサ」とネットに触れる音で、ハクビシンも警戒してくれるはずです。
ただし、完璧を期すなら両方使うのがベスト。
金属ガードで幹を守りつつ、ネットで全体を覆う。
これで「ダブルガード」の完璧防御になります。
りんごを守る鉄壁の守りの完成です!
落下果実の放置は「大きな誘因」になる危険性
落下果実を放置するのは、ハクビシンにとって「いらっしゃいませ〜」と大きな看板を出しているようなものです。絶対にやめましょう!
「え?落ちたりんごくらいいいじゃない」と思うかもしれません。
でも、これが実は大問題なんです。
落下果実は、ハクビシンを引き寄せる強力な誘因になってしまいます。
なぜそんなに危険なのか、詳しく見ていきましょう。
- ハクビシンの大好物:落下果実は地面にあるので、簡単に食べられます。
- 匂いの発信源:腐り始めたりんごは強い匂いを放ち、ハクビシンを誘います。
- 餌場の記憶:一度餌を見つけた場所は、ハクビシンの頭にしっかり記憶されます。
- 繰り返しの来訪:美味しい思いをした場所には、何度も戻ってきます。
- 仲間への伝達:ハクビシンは仲間に餌場の情報を伝えることがあります。
では、どうすればいいのでしょうか?
対策は簡単です。
毎日こまめに落下果実を拾い集めることです。
「面倒くさいな〜」と思うかもしれません。
でも、これが本当に大切なんです。
- 朝晩の見回り時に必ず拾う
- 腐ったりんごは深く埋めるか、しっかり処分する
- 落下防止ネットを設置して、拾いやすくする
木の下に細かい網目のネットを張ることで、りんごが地面に直接落ちるのを防ぎます。
「カポッ」と音がしたら、すぐに回収できますよ。
この小さな努力が、大きな被害を防ぐ鍵になるんです。
毎日の積み重ねで、ハクビシンに「ここには美味しいものはないよ」とアピールしましょう。
そうすれば、きっとハクビシンも諦めてどこかへ行ってしまうはずです。
忌避剤の効果は「一時的」vs「持続的」な対策
忌避剤、使ってみたけど効果がいまいち…そんな経験ありませんか?実は、忌避剤には「一時的」な効果しかないんです。
でも、諦めないでください!
持続的な対策と組み合わせれば、効果は格段に上がります。
まず、忌避剤の特徴を見てみましょう。
- 強い匂いや味でハクビシンを寄せ付けない
- すぐに効果が出る
- 使いやすい
でも、ここに落とし穴があるんです。
忌避剤の最大の弱点は、効果が長続きしないこと。
雨で流されたり、日光で分解されたりして、すぐに効果がなくなってしまいます。
さらに、ハクビシンは賢い動物。
同じ忌避剤を使い続けると、すぐに慣れてしまうんです。
「えー、じゃあ意味ないじゃん」と思わないでください。
忌避剤は、他の対策と組み合わせることで真価を発揮します。
持続的な対策の例を見てみましょう。
- 物理的な防御:ネットや金属ガードの設置
- 環境整備:落下果実の除去、木の剪定
- 光や音による威嚇:センサーライトの設置
- 自然な忌避効果:ハーブの植栽
例えば、ハクビシンの活動が活発になる時期や、新しい被害の痕跡を見つけたときに集中的に使用する。
そうすることで、効果を最大限に引き出せます。
忌避剤の使い方のコツは、「変化をつける」こと。
- 複数の種類の忌避剤を交互に使う
- 散布する場所や量を変える
- 天気や季節に合わせてタイミングを調整する
「なるほど、忌避剤も使い方次第なんだ!」そうなんです。
一時的な効果を持続的な対策で補強する。
これが、ハクビシン対策の黄金パターンなんです。
さぁ、あなたも忌避剤を味方につけて、りんご園を守りましょう!
木の剪定vs繁茂!どちらがハクビシン対策に有効か
木の剪定と繁茂、どっちがハクビシン対策に効果的か悩んでいませんか?結論から言うと、適度な剪定が効果的です。
でも、やりすぎは逆効果になるので要注意です!
「えっ、剪定しすぎるとダメなの?」と思われるかもしれません。
実は、剪定の仕方によって、ハクビシンの行動が大きく変わってしまうんです。
まず、適度な剪定のメリットを見てみましょう。
- 見通しが良くなり、ハクビシンの姿を発見しやすい
- 枝の重なりが減り、ハクビシンの移動を制限できる
- 風通しが良くなり、病気や害虫の発生を抑制できる
- 実のなり具合が良くなり、品質の高いりんごが育つ
そうなんです。
でも、ここで罠があります。
剪定しすぎると、逆にハクビシンを喜ばせてしまうんです。
剪定しすぎのデメリットはこんな感じ。
- 枝が少なくなり、ハクビシンが簡単に木に登れるようになる
- 隠れ場所がなくなり、ハクビシンが警戒心を持たなくなる
- 日光が直接当たり、りんごの実が早く熟してしまう
- 木の生育バランスが崩れ、翌年の収穫量が減る可能性がある
でも、大丈夫です。
コツさえつかめば、誰でも上手に剪定できます。
適度な剪定のポイントはこちら。
- 樹形を乱さない程度に、込み入った枝を間引く
- 地面から1.5m以下の低い枝は残す(ハクビシンの侵入を防ぐ障害物に)
- 枝と枝の間隔を30cm程度空ける(ハクビシンの移動を難しくする)
- 剪定は冬場に行い、春までに傷を癒合させる
そうなんです。
これで、ハクビシン対策と木の健康、両方をケアできます。
繁茂させすぎるのも問題です。
枝葉が密集しすぎると、ハクビシンの絶好の隠れ家になってしまいます。
「ガサガサ」という音がしても、どこにいるのか分からない。
そんな状況は避けたいですよね。
適度な剪定で、ハクビシンに「ここは住みにくいぞ」とアピールしつつ、りんごの木も健康に保つ。
これが、剪定の極意なんです。
さぁ、あなたもプロの剪定師の気分で、りんごの木のお手入れをしてみませんか?
夜間の見回りvs自動センサーライト!効果を比較
夜間の見回りと自動センサーライト、どっちがハクビシン対策に効果的か迷っていませんか?結論から言うと、両方とも効果はありますが、自動センサーライトの方がおすすめです。
「えっ、人間の目より機械の方が良いの?」と思われるかもしれません。
実は、ハクビシン対策には人間の目よりも、コンスタントな監視が重要なんです。
まずは、夜間の見回りのメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット:
- その場で状況を詳しく確認できる
- 即座に対応ができる
- ハクビシンの行動パターンを直接観察できる
- 体力的な負担が大きい
- 毎晩続けるのは難しい
- ハクビシンと遭遇する危険性がある
- 人間の気配で警戒されてしまう
その通りです。
一方で、自動センサーライトはどうでしょうか?
メリット:
- 24時間365日、休みなく監視できる
- 突然の光でハクビシンを驚かせる
- 電気代が安く、維持費が少ない
- 設置が簡単で、手間がかからない
- 人間が直接関与しないので、ハクビシンが慣れにくい
- 誤作動の可能性がある(猫や風で反応など)
- 電池切れや故障のリスクがある
- 設置場所によっては、効果が限定的
その通りです。
自動センサーライトは、小さな投資で大きな効果が得られる優れものなんです。
では、どんなセンサーライトを選べばいいのでしょうか?
ポイントをいくつか紹介しましょう。
- 明るさは100ルーメン以上を選ぶ(ハクビシンを十分に驚かせられる明るさ)
- 検知範囲が広いもの(少なくとも半径5m以上)
- 防水機能付きのもの(雨でも安心)
- 電池式よりソーラー充電式がおすすめ(電池交換の手間が省ける)
これらのポイントを押さえたセンサーライトを、りんごの木の周りに数か所設置すれば、ハクビシン対策はバッチリです。
ただし、センサーライトだけに頼りきりになるのは避けましょう。
時々は自分の目で確認することも大切です。
例えば、週に1回程度、夕方にりんご園を見回ってみるのはどうでしょうか?
ライトの動作確認もできますし、思わぬ発見があるかもしれません。
「よし、センサーライトと時々の見回りで完璧だね!」その意気込みが素晴らしいです。
この方法で、あなたのりんご園はハクビシンにとって「入りにくい場所」になること間違いなしです。
さぁ、明るく安全なりんご園作りを始めましょう!
驚きの裏技!意外なアイテムでハクビシン対策
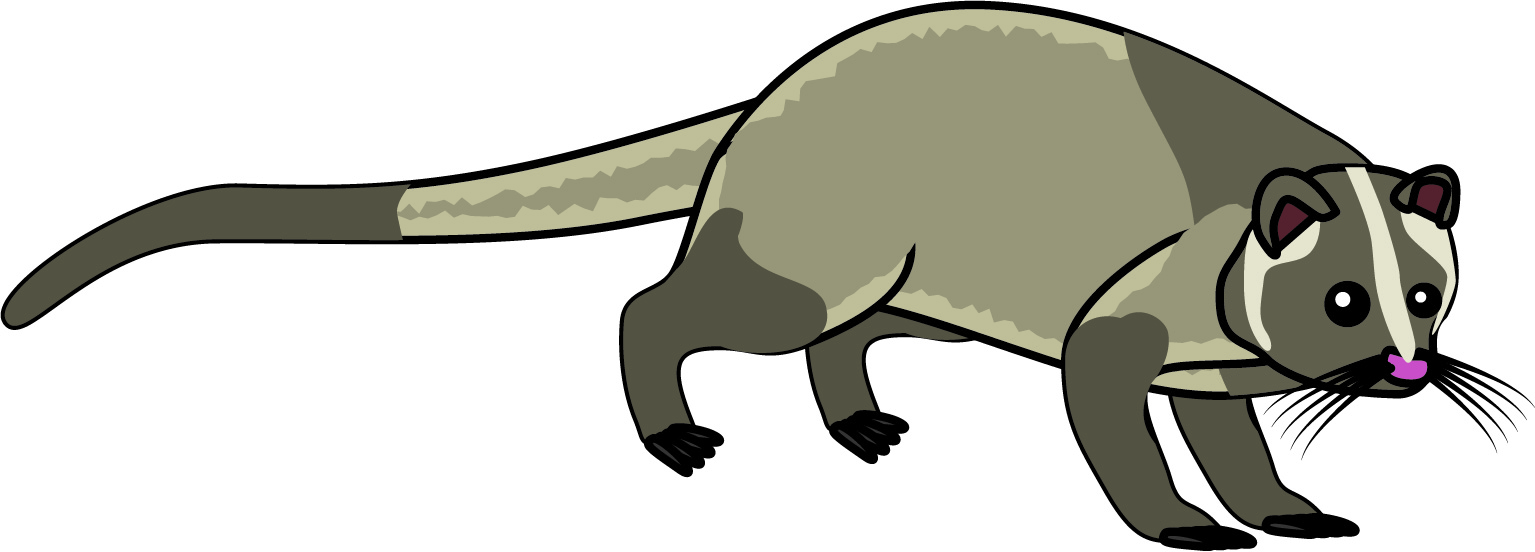
ラベンダーの香りで「自然な忌避効果」を実現
ラベンダーの香りは、ハクビシンを寄せ付けない自然な忌避効果があります。この意外な裏技で、りんご園を守りましょう。
「え?ラベンダーでハクビシン対策?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが実は効果的なんです。
ハクビシンは嗅覚が鋭いため、強い香りが苦手。
ラベンダーの香りは、まさにハクビシンにとっての「立入禁止サイン」なんです。
ラベンダーを使ったハクビシン対策のポイントは以下の通りです。
- りんごの木の周りにラベンダーを植える
- ラベンダーオイルを染み込ませた布を木に吊るす
- ラベンダーの乾燥花をネットに入れて設置する
- ラベンダーの香りのするスプレーを定期的に散布する
安心してください。
ラベンダーの香りはりんごの味や香りに影響を与えません。
むしろ、害虫対策にもなる一石二鳥の効果があるんです。
使い方のコツは、定期的に香りを更新すること。
例えば、2週間に1回程度、新しいラベンダーに植え替えたり、オイルを補充したりすると良いでしょう。
「ふわっ」と香る心地よいラベンダーの香り。
人間にはリラックス効果がありますが、ハクビシンには「ここには近づかないぞ」というメッセージになるんです。
この自然な方法で、化学薬品を使わずにハクビシン対策ができるんです。
りんご園が、美しいラベンダーの香りに包まれる様子を想像してみてください。
ハクビシンを寄せ付けない、素敵なりんご園の完成です!
風船の動きと音で「ハクビシンを威嚇」する方法
風船を使ってハクビシンを威嚇する?これ、意外と効果的なんです。
動きと音で、ハクビシンを寄せ付けません。
「え?そんな簡単なもので効果があるの?」と思われるかもしれません。
でも、実はハクビシンは新しい物や予測できない動きを非常に警戒するんです。
風船は、まさにそんなハクビシンの苦手なものの代表格なんです。
風船を使ったハクビシン対策の方法を見てみましょう。
- 大きめの風船を選ぶ(直径30cm以上がおすすめ)
- 風船に目玉模様を描く(捕食者を連想させる効果あり)
- 細い紐で風船をりんごの木に吊るす
- 複数の風船を異なる高さに設置する
- 定期的に風船の位置を変える
これがハクビシンにとっては「何か怖いものがいる!」というサインになるんです。
特に効果的なのは、夜間に光る風船を使うこと。
暗闇で不気味に光る風船は、ハクビシンの警戒心を一層高めます。
「キラキラ」と光る風船は、ハクビシンにとっては正体不明の恐ろしい存在に見えるんです。
ただし、注意点もあります。
風船は1〜2週間で空気が抜けてしまうので、定期的に交換が必要です。
また、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することも忘れずに。
「こんな簡単なことで本当にハクビシンが来なくなるの?」と半信半疑かもしれません。
でも、試してみる価値は十分にあります。
費用も手間もかからず、すぐに始められる対策なんです。
さあ、あなたのりんご園に、カラフルで楽しい「ハクビシン撃退風船」を飾ってみましょう!
LEDソーラーライトで「夜間の侵入」を阻止
夜の闇に浮かぶ不思議な光。それがLEDソーラーライトです。
この光で、ハクビシンの夜間侵入を効果的に防ぐことができます。
「え?ライトを付けるだけでいいの?」と思われるかもしれません。
実は、ハクビシンは明るい場所を本能的に避ける習性があるんです。
暗闇を好む夜行性動物のハクビシンにとって、突然の明かりは大きな脅威。
これを利用した作戦なんです。
LEDソーラーライトを使ったハクビシン対策のポイントは以下の通りです。
- 人感センサー付きのライトを選ぶ
- 明るさは100ルーメン以上のものを使用
- りんごの木の周りに複数設置する
- ライトの向きを様々な角度に調整する
- 定期的にソーラーパネルの汚れを拭き取る
「ピカピカ」と不規則に点滅する光は、ハクビシンをより一層怯えさせます。
まるで、「ここは危険だぞ!」と警告を発しているようなものです。
設置場所も重要です。
りんごの木の幹や主要な枝に向けてライトを設置すると、ハクビシンの侵入経路を直接照らすことができます。
「えいっ」と木に登ろうとしたハクビシンが、突然の光に驚いて逃げ出す様子が目に浮かびますね。
ただし、近隣住民への配慮も忘れずに。
強すぎる光は迷惑になる可能性があるので、光の向きや強さには注意しましょう。
「でも、電気代が心配...」という声が聞こえてきそうです。
安心してください。
ソーラー式なので電気代はかかりません。
昼間の太陽光で充電し、夜間に自動で点灯する仕組みです。
エコで経済的、そしてハクビシン対策にも効果的。
まさに一石三鳥のアイテムなんです。
さあ、あなたのりんご園を、夜の守護者LEDソーラーライトで守りましょう。
ハクビシンを寄せ付けない、光り輝くりんご園の完成です!
ペットボトルの反射光で「目くらまし効果」を狙う
ペットボトルを使ってハクビシン対策?実は、これが意外と効果的なんです。
反射光による目くらまし効果で、ハクビシンを寄せ付けません。
「え?ただのペットボトルでそんなことができるの?」と驚かれるかもしれません。
でも、実はこれ、昔から農家さんたちが使ってきた知恵なんです。
ハクビシンは予測できない光の動きを非常に警戒します。
ペットボトルの反射光は、まさにそんなハクビシンの苦手なものなんです。
ペットボトルを使ったハクビシン対策の方法を見てみましょう。
- 透明なペットボトルを用意する(1.5〜2リットルサイズがおすすめ)
- ペットボトルに水を半分ほど入れる
- ボトルの外側にアルミホイルを巻き付ける(反射効果アップ!
) - 細い紐でペットボトルをりんごの木に吊るす
- 複数のペットボトルを異なる高さに設置する
「キラキラ」「ピカピカ」と光る様子は、ハクビシンにとって正体不明の恐ろしいものに見えるんです。
特に効果的なのは、夜間の月明かりを利用すること。
静かな夜のりんご園で、月光を反射して揺れるペットボトル。
幻想的な光景ですが、ハクビシンにとっては恐怖の的です。
ただし、注意点もあります。
ペットボトルは紫外線で劣化するので、2〜3ヶ月に一度は新しいものに交換しましょう。
また、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することも大切です。
「こんな簡単なもので本当にハクビシンが来なくなるの?」と半信半疑かもしれません。
でも、試してみる価値は十分にあります。
費用もほとんどかからず、すぐに始められる対策なんです。
さあ、あなたのりんご園に、キラキラ輝く「ハクビシン撃退ペットボトル」を飾ってみましょう。
エコで経済的、そして効果的。
三拍子揃った素晴らしいハクビシン対策の完成です!
古いCDを活用した「光の壁」でハクビシンを撃退
古いCDが、ハクビシン対策の強い味方になります。CDの反射光で作る「光の壁」が、ハクビシンを効果的に撃退してくれるんです。
「え?捨てようと思っていたCDが役に立つの?」と驚かれるかもしれません。
実は、CDの表面は光を強く反射する特性があり、これがハクビシンを驚かせるのに最適なんです。
ハクビシンは予期せぬ光の動きを非常に警戒します。
CDの反射光は、まさにハクビシンの天敵と言えるでしょう。
CDを使ったハクビシン対策の方法を詳しく見てみましょう。
- 使わなくなったCDを集める(10枚以上あるとより効果的)
- CDに小さな穴を開け、紐を通す
- りんごの木の枝にCDを吊るす(高さを変えて設置するのがコツ)
- CDの間隔は30〜50cm程度に保つ
- 風で自由に動くよう、ゆるめに結ぶ
「キラキラ」「ピカピカ」と光る様子は、ハクビシンにとって正体不明の恐ろしい存在に見えるんです。
まるで、りんごの木の周りに「光の壁」ができたかのよう。
特に効果的なのは、複数のCDを使って立体的に配置することです。
上下左右に光が動く様子は、ハクビシンの目を惑わせ、近づく勇気を失わせます。
「ギラギラ」と輝くCDの群れは、ハクビシンにとっては恐ろしい光の迷路のように感じられるでしょう。
ただし、注意点もあります。
CDは強い日差しで劣化するので、3〜4ヶ月に一度は新しいものに交換しましょう。
また、近隣への配慮も忘れずに。
反射光が強すぎると迷惑になる可能性があるので、設置場所には気を付けましょう。
「本当にこんな簡単なことでハクビシンが来なくなるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
でも、多くの農家さんが実際に効果を実感しているんです。
費用もかからず、すぐに始められる対策。
さあ、あなたのりんご園を、キラキラ輝く「ハクビシン撃退CD」で守ってみませんか?
捨てるはずだったCDが、りんごの守護者に大変身。
エコで効果的なハクビシン対策の完成です!