ハクビシンを追い払っても戻ってくる?【餌と隠れ場所が原因】再侵入を防ぐ長期的対策3つ

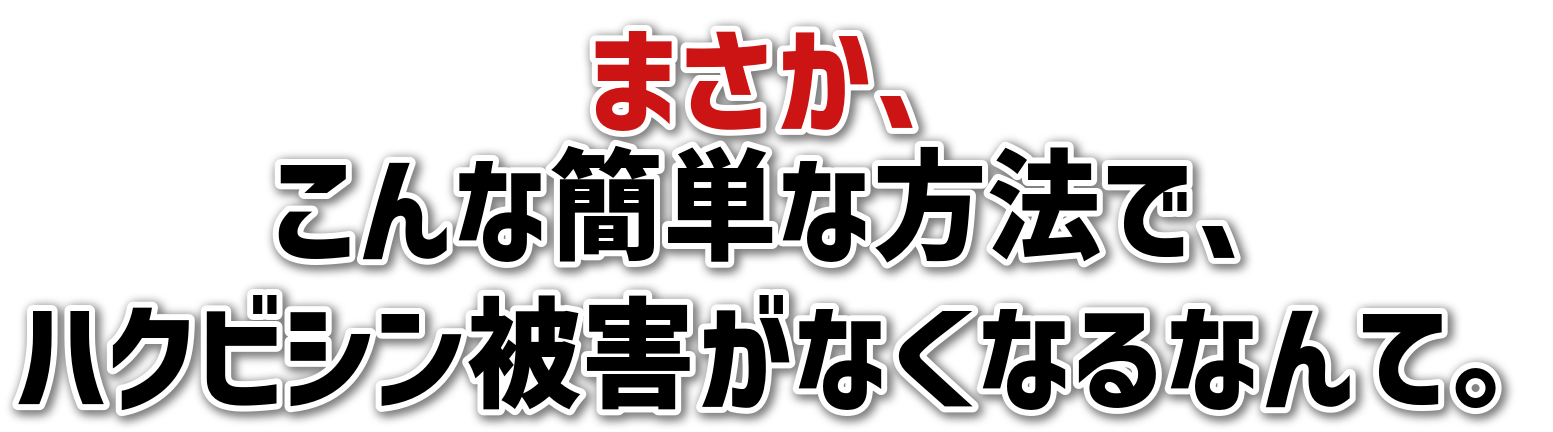
【この記事に書かれてあること】
ハクビシンを追い払ったのに、また戻ってくる…。- ハクビシンが再侵入する主な原因は餌と隠れ場所の存在
- 物理的防御と忌避剤の効果を長期的視点で比較
- 音と光を使った撃退方法の効果の違いを解説
- 地域ぐるみの対策が持続的な効果につながる
- 意外な素材を使った10の撃退法を紹介
そんな経験はありませんか?
実は、ハクビシンが再び現れる原因には、餌と隠れ場所が深く関わっているんです。
一時的な対策では根本解決にならないのです。
でも、ご安心ください。
この記事では、ハクビシンが戻ってくる理由を詳しく解説し、効果的な長期対策をご紹介します。
さらに、意外な素材を使った10の撃退法も公開!
これであなたの家も、ハクビシンにとって「二度と寄りつきたくない場所」に変身します。
さあ、一緒にハクビシン撃退作戦を始めましょう!
【もくじ】
ハクビシンの再侵入を招く原因と対策ポイント

追い払っても戻ってくる!餌と隠れ場所が主因
ハクビシンが追い払っても戻ってくる主な原因は、餌と隠れ場所の存在です。これらが確保されている限り、ハクビシンにとって魅力的な環境だと認識され続けてしまうのです。
「せっかく追い払ったのに、また来ちゃった…」とため息をつく方も多いのではないでしょうか。
実は、ハクビシンは非常に賢く、一度居心地の良い場所を見つけると、簡単には諦めないんです。
では、具体的にハクビシンを引き寄せてしまう要因を見ていきましょう。
- 豊富な餌源:果物、野菜、小動物、ペットフード、生ゴミなど
- 快適な隠れ場所:屋根裏、物置、樹洞など暗くて暖かい閉鎖的な空間
- 安全な環境:人や天敵からの脅威が少ない場所
「うちの庭、ハクビシンにとっては天国みたいなものかも…」なんて思い当たる節はありませんか?
対策の第一歩は、この「ハクビシン天国」を「ハクビシン地獄」に変えることです。
餌源を徹底的に除去し、隠れ場所をなくすことで、ハクビシンにとって魅力のない環境づくりを心がけましょう。
そうすれば、追い払った後も戻ってこない可能性がグンと高まります。
ハクビシンが好む「魅力的な環境」の特徴とは
ハクビシンが好む「魅力的な環境」の特徴は、豊富な食べ物と安全な住処が整っていることです。この2つの条件が満たされると、ハクビシンにとっては理想的な生活圏となってしまいます。
「まさか、うちの庭がハクビシンのリゾート地になっているなんて…」と驚く方もいるかもしれません。
でも、実はその可能性は十分にあるんです。
ハクビシンが好む環境の特徴を詳しく見ていきましょう。
- 食べ物が豊富
- 果樹園や家庭菜園がある
- 生ゴミの放置や野外でのペットフード給餌
- 小動物(昆虫やカエルなど)が多い
- 安全な隠れ場所がある
- 屋根裏や壁の隙間
- 物置や倉庫の隅
- 大きな樹木の樹洞
- 水場がある
- 池や小川
- 雨水がたまりやすい場所
- 人間の干渉が少ない
- 夜間に人の出入りが少ない
- 騒音や明るい照明がない
「うちの庭、まるでハクビシンのオールインクルーシブリゾートみたい…」なんて思い当たる節はありませんか?
対策としては、これらの条件をできるだけ取り除くことが重要です。
例えば、果物や野菜の収穫をこまめに行い、落果を放置しない。
生ゴミの管理を徹底し、ペットフードは屋内で与える。
屋根や外壁の隙間を塞ぎ、物置や倉庫の戸締まりを確実にする。
このような取り組みで、ハクビシンにとっての「魅力」を減らしていくことができるんです。
再侵入を防ぐ!餌と隠れ場所の徹底排除法
ハクビシンの再侵入を防ぐ最も効果的な方法は、餌と隠れ場所を徹底的に排除することです。これにより、ハクビシンにとって魅力的な環境をなくし、再び戻ってくる可能性を大幅に減らすことができます。
「でも、具体的にどうすればいいの?」と思う方も多いでしょう。
心配ありません。
ここでは、実践的な排除法をいくつかご紹介します。
まずは、餌の排除から始めましょう。
- 果物や野菜の管理:収穫をこまめに行い、落果は速やかに処理する
- 生ゴミの適切な処理:密閉容器を使用し、夜間は屋外に放置しない
- ペットフードの管理:屋内で与え、食べ残しは片付ける
- コンポストの対策:蓋付きの容器を使用し、肉や魚の残渣は入れない
- 屋根や外壁の点検:隙間や穴を見つけたら速やかに修理する
- 物置や倉庫の管理:戸締まりを徹底し、内部を整理整頓する
- 庭木の手入れ:枝の剪定を行い、樹洞があれば塞ぐ
- 庭の整備:不要な物を片付け、ハクビシンの隠れ場所をなくす
ただし、注意点もあります。
一度に全てを完璧にするのは難しいかもしれません。
でも、できることから少しずつ始めていけば、確実に効果は表れます。
「ちょっとずつでも、コツコツと対策を続けよう」という気持ちが大切です。
そうすれば、いつの日か「あれ?最近ハクビシンを見かけなくなったぞ」と気づく日が来るはずです。
頑張りましょう!
ハクビシン対策は「個人努力」だけでは不十分!
ハクビシン対策は個人の努力だけでは十分な効果が得られません。なぜなら、ハクビシンの行動範囲は広く、周辺地域全体で取り組む必要があるからです。
「え?自分の家だけ対策しても意味がないの?」と落胆する方もいるかもしれません。
でも、ご安心ください。
個人の努力は決して無駄ではありません。
ただ、より効果的な対策には地域ぐるみの取り組みが欠かせないんです。
では、なぜ地域全体での対策が重要なのでしょうか?
- ハクビシンの行動範囲が広い
- 半径1〜2km程度の範囲を活動エリアとする
- 1軒だけ対策しても、隣家に移動するだけ
- 餌場と隠れ場所の分散
- 複数の家や場所を利用して生活する
- 一箇所で餌がなくなっても、他の場所で補う
- 繁殖と個体数増加
- 年2回の繁殖期があり、個体数が増加しやすい
- 地域全体で管理しないと、population爆発の恐れ
以下に、いくつかのアイデアをご紹介します。
- 情報共有の仕組み作り:町内会やSNSグループで目撃情報を共有
- 一斉清掃の実施:定期的に地域全体で餌源となるゴミを撤去
- フェンス設置の協力:隣接する家同士で連続したフェンスを設置
- 果樹の管理ルール作り:落果の処理や収穫時期の調整を地域で統一
- 共同での忌避剤散布:効果的なタイミングと場所を協議して実施
そして、その連帯感が地域全体の防衛力を高めていくんです。
ただし、注意点もあります。
隣人との関係性を損なわないよう、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
「ハクビシン対策」という共通の目標に向かって、地域の絆を深める良い機会にもなるはずです。
一緒に頑張りましょう!
長期的な視点で考えるハクビシン撃退戦略
物理的防御vs忌避剤!効果の持続性を比較
ハクビシン対策では、物理的防御の方が忌避剤よりも長期的な効果が期待できます。でも、両方を組み合わせるのがベストな選択肢なんです。
「えっ、どっちかを選ばなきゃいけないの?」なんて思った方もいるかもしれませんね。
安心してください。
実は、両方の良いところを取り入れることで、より強力な対策になるんです。
まずは、物理的防御と忌避剤のそれぞれの特徴を見てみましょう。
- 物理的防御
- 効果の持続性:とても高い
- メンテナンス頻度:低い
- 初期費用:比較的高い
- 忌避剤
- 効果の持続性:一時的
- メンテナンス頻度:高い(定期的な再散布が必要)
- 初期費用:比較的低い
一方、忌避剤は強い匂いや味で寄せ付けない効果があります。
「じゃあ、物理的防御だけでいいんじゃない?」と思うかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
実は、両方を組み合わせることで、より効果的な対策になるんです。
例えば、フェンスを設置しつつ、その周辺に忌避剤を散布する。
こうすることで、物理的な障壁と心理的な障壁の両方を作り出せるんです。
ハクビシンにとっては、まるで「難攻不落の城」のような印象を与えることができるわけです。
ただし、忘れてはいけないのが定期的なメンテナンスです。
物理的防御も時間とともに劣化する可能性がありますし、忌避剤は効果が薄れてくるので再散布が必要です。
「よし、これで完璧!」と油断せずに、定期的なチェックを心がけましょう。
音による撃退vs光による撃退!どちらが長期的
ハクビシンの撃退方法として、光による撃退の方が音による撃退よりも長期的な効果が期待できます。ただし、両方を組み合わせることで、より強力な対策となります。
「えー、音の方が効果ありそうじゃない?」なんて思った方もいるかもしれませんね。
でも、実はハクビシンは音には比較的早く慣れてしまうんです。
一方、光は不規則に点滅させることで、より長期的な効果を維持できるんです。
それでは、音と光による撃退方法の特徴を詳しく見てみましょう。
- 音による撃退
- 即効性:高い
- 長期的効果:低い(慣れやすい)
- 範囲:広い
- 近隣への影響:要注意(騒音問題の可能性)
- 光による撃退
- 即効性:中程度
- 長期的効果:高い(慣れにくい)
- 範囲:局所的
- 近隣への影響:比較的少ない
一方、光による撃退は、センサーライトや点滅するLEDライトなどを使用します。
ここで、ちょっとした裏技をご紹介します。
実は、音と光を組み合わせることで、より効果的な撃退が可能なんです。
例えば、センサーライトに小さなブザーを取り付ける。
こうすることで、光と音の両方でハクビシンを驚かせることができるんです。
ただし、注意点もあります。
特に音を使う場合は、近隣への配慮が必要です。
「よっしゃ、これで撃退だ!」と張り切って大音量で音を鳴らしたら、ご近所トラブルの原因になりかねません。
適切な音量調整と、使用時間帯への配慮を忘れずに。
光による撃退の場合も、強すぎる光は近隣の方の迷惑になる可能性があります。
適度な明るさと、できるだけ自宅の敷地内に光が収まるよう調整しましょう。
こうした工夫を重ねることで、ハクビシンにとっては「ここは居心地が悪い」と感じさせ、長期的な撃退効果を期待できるんです。
がんばって対策を続けましょう!
化学的忌避剤vs自然由来の忌避剤!持続性の差
ハクビシン対策における忌避剤の選択では、化学的忌避剤の方が自然由来の忌避剤よりも効果の持続性が高いです。ただし、環境への配慮や安全性を考えると、両方をうまく使い分けるのがおすすめです。
「え?自然のものの方が効くんじゃないの?」なんて思った方もいるかもしれませんね。
確かに自然由来の忌避剤は安全性が高く、環境にも優しいのですが、効果の持続時間が短いのが難点なんです。
では、化学的忌避剤と自然由来の忌避剤の特徴を詳しく見てみましょう。
- 化学的忌避剤
- 効果の持続性:高い(数週間から数か月)
- 効果の強さ:強い
- 環境への影響:要注意
- コスト:比較的高い
- 自然由来の忌避剤
- 効果の持続性:低い(数日から1週間程度)
- 効果の強さ:穏やか
- 環境への影響:少ない
- コスト:比較的安い
一方、自然由来の忌避剤には、唐辛子やニンニク、木酢液などがあります。
ここで、ちょっとした使い分けのコツをお教えしましょう。
実は、場所によって使う忌避剤を変えるのが効果的なんです。
例えば、家の周りの重要なポイントには化学的忌避剤を使い、庭の植物の近くには自然由来の忌避剤を使う。
こうすることで、効果的な防御ラインを作りつつ、環境への影響も最小限に抑えられるんです。
ただし、注意点もあります。
化学的忌避剤を使う場合は、使用方法をしっかり守ることが大切です。
「よし、たくさん撒けば効果バツグン!」なんて考えは禁物。
適量を守り、子どもやペットが触れない場所に使用しましょう。
自然由来の忌避剤の場合は、こまめな再散布が必要です。
「一度撒いたからもう大丈夫」なんて油断は禁物。
特に雨が降った後は効果が薄れやすいので、すぐに再散布するのがポイントです。
「えー、面倒くさそう…」なんて思った方もいるかもしれません。
でも、こつこつと対策を続けることで、徐々にハクビシンを寄せ付けない環境が作れるんです。
根気強く続けていきましょう!
ハクビシン対策と近隣トラブル!両立のコツ
ハクビシン対策と近隣との良好な関係は、しっかりとしたコミュニケーションを取ることで両立できます。お互いの理解と協力が、効果的な対策の鍵となるんです。
「えっ、ハクビシン対策で近所トラブル?」なんて思った方もいるかもしれません。
でも、実は防犯ブザーやセンサーライトの設置など、一部の対策方法が近隣の方々に迷惑をかける可能性があるんです。
では、ハクビシン対策と近隣トラブルを防ぐためのポイントを見ていきましょう。
- 事前の説明と相談
- 対策の必要性を丁寧に説明
- 使用する方法について相談
- 影響を受ける可能性のある隣家には個別に話をする
- 対策方法の工夫
- 音を使う場合は、音量と使用時間に配慮
- 光を使う場合は、方向と強さを調整
- 臭いの強い忌避剤は、敷地の内側で使用
- 情報共有と協力体制の構築
- 被害状況や対策効果を定期的に共有
- 地域ぐるみでの取り組みを提案
- 成功事例を積極的に紹介
例えば、センサーライトを設置する際、隣家の寝室の窓に光が直接当たらないよう角度を調整する。
または、音を使う対策の場合、夜中は音量を下げるなどの配慮をする。
こういった小さな工夫が、大きなトラブル防止につながるんです。
「でも、ご近所さんが協力的じゃなかったら…」なんて不安に思う方もいるかもしれません。
そんな時こそ、粘り強くコミュニケーションを取ることが大切です。
例えば、こんな会話はどうでしょうか。
「山田さん、実はうちにハクビシンが出るんです。困っていて…何か良い対策方法ないでしょうか?」
このように、一方的に自分の対策を押し付けるのではなく、相手の意見も聞きながら進めていくのがポイントです。
時には「私の家は大丈夫だから」と協力的でない方もいるかもしれません。
そんな時は、「でも、ハクビシンの行動範囲は広いんです。今は大丈夫でも、将来的に被害が広がる可能性があるんですよ」と、地域全体の問題として捉えてもらえるよう説明するのも効果的です。
こうした丁寧なコミュニケーションを重ねることで、「ハクビシン対策」が「地域の絆を深める機会」に変わるかもしれません。
一緒に頑張りましょう!
意外と簡単!驚きのハクビシン撃退法5選

光の反射で威嚇!「ペットボトル反射板」作戦
ペットボトルを使った反射板は、ハクビシンを驚かせる効果的な撃退法です。身近な材料で簡単に作れるのが魅力です。
「えっ、ペットボトルでハクビシンが撃退できるの?」と思った方も多いでしょう。
実は、ハクビシンは光に敏感な生き物なんです。
特に、不規則に動く光は彼らを不安にさせるんですよ。
では、具体的な作り方と設置方法を見ていきましょう。
- 用意するもの
- 空のペットボトル(1.5〜2リットル)
- 水
- ひも
- 作り方
- ペットボトルを洗って乾かす
- ボトルに水を半分ほど入れる
- ふたをしっかり閉める
- ひもでボトルを縛る
- 設置方法
- 庭木や柵にぶら下げる
- 複数個所に設置する
- 風で揺れやすい場所を選ぶ
風で揺れるペットボトルの中の水が、月明かりや街灯の光を不規則に反射させるんです。
この予測不能な光の動きが、ハクビシンを怖がらせる効果があるんです。
「でも、うちの庭は暗いから効果ないかも…」なんて心配する必要はありません。
実は、ハクビシンの目は薄暗い中でもよく見えるんです。
だから、ほんの少しの光でも十分効果があるんですよ。
ただし、注意点もあります。
強風の日はペットボトルが飛ばされる可能性があるので、しっかりと固定しましょう。
また、近隣の方への配慮も忘れずに。
反射光が隣家に入らないよう、角度調整も大切です。
この方法のいいところは、材料費がほとんどかからないこと。
そして、いつでも簡単に作り直せること。
定期的に新しいものと交換すれば、より効果が持続しますよ。
さあ、今すぐ家にあるペットボトルを活用して、ハクビシン撃退作戦を始めましょう!
音と光のダブル効果!「アルミホイル巻き」技
アルミホイルを木の幹に巻き付ける方法は、音と光の両方でハクビシンを撃退する効果があります。簡単で低コストなのに、意外と強力な対策なんです。
「えー、アルミホイルってあの台所にあるやつ?」と驚く方も多いでしょう。
そうなんです。
普段お料理に使うアルミホイルが、実はハクビシン対策の強い味方になるんですよ。
では、具体的な方法と効果を見ていきましょう。
- 用意するもの
- アルミホイル(幅30cm以上のものがおすすめ)
- ガムテープまたは紐
- 設置方法
- 木の幹の地上1〜1.5mの高さにアルミホイルを巻く
- 幅20〜30cm程度の帯状に巻く
- 端をガムテープや紐でしっかり固定する
- 複数の木に設置する
- 効果の仕組み
- 光の反射:月明かりや街灯の光を不規則に反射
- 音の発生:風で揺れる際にカサカサ音を立てる
- 触覚刺激:ハクビシンが木を登ろうとした時に違和感を与える
光の反射は視覚を、カサカサ音は聴覚を、そして触れた時の違和感は触覚を刺激します。
これらが組み合わさることで、ハクビシンに「ここは危険だ!」というメッセージを送るわけです。
「でも、見た目が悪くないかな…」と心配する方もいるでしょう。
確かに、最初は少し目立つかもしれません。
でも、時間が経つにつれて周囲の景色に溶け込んでいきます。
それに、効果を考えれば、少しの見た目の犠牲は許容範囲ではないでしょうか。
ただし、注意点もあります。
強風の日はアルミホイルが破れたり外れたりする可能性があるので、定期的に点検と補修が必要です。
また、鳥や小動物にも影響を与える可能性があるので、生態系への配慮も忘れずに。
この方法の素晴らしいところは、材料費がとても安いこと。
そして、誰でも簡単に設置できること。
さらに、効果が目に見えてわかりやすいんです。
「よし、今すぐやってみよう!」そんな気持ちになりませんか?
ぜひ試してみてください。
きっと、思った以上の効果を実感できるはずですよ。
強烈な香りで撃退!「コーヒーかす散布」法
コーヒーかすを庭にまくことで、その強い香りでハクビシンを遠ざけることができます。家庭にある材料を再利用できる、エコでお財布にも優しい対策法なんです。
「えっ、コーヒーかすってゴミじゃないの?」と思った方も多いでしょう。
実は、このいわゆる"ゴミ"が、ハクビシン対策の強い味方になるんです。
しかも、土壌改良にも役立つ一石二鳥の方法なんですよ。
では、具体的な使い方と効果を見ていきましょう。
- 準備するもの
- 乾燥させたコーヒーかす
- スコップやじょうろ(散布用)
- 使用方法
- コーヒーかすを天日で十分に乾燥させる
- ハクビシンが出没する場所や通り道に散布する
- 木の根元や植え込みの周りにも重点的に撒く
- 雨が降った後は再度散布する
- 効果の仕組み
- 強い香りがハクビシンの嗅覚を刺激する
- 土壌の pH を変化させ、ハクビシンの好まない環境を作る
- 昆虫を寄せ付けにくくし、ハクビシンの餌を減らす
彼らは人間の10倍以上の嗅覚を持っているんです。
私たちには心地よい香りでも、ハクビシンにとっては強烈すぎて近寄りがたい臭いなんですね。
「でも、うちはコーヒーをあまり飲まないんだけど…」そんな心配は無用です。
近所のカフェに相談してみるのもいいでしょう。
多くのお店で、コーヒーかすを無料で譲ってくれることがあります。
ただし、注意点もあります。
コーヒーかすは湿気を含むと発酵してしまい、かえってハクビシンを引き寄せる可能性があります。
だから、必ず十分に乾燥させてから使用することが大切です。
この方法の素晴らしいところは、ゴミの削減にもつながること。
そして、土壌改良の効果も期待できること。
まさに一石二鳥、いや一石三鳥の対策法と言えるでしょう。
「よーし、明日からコーヒーかすを集めてみよう!」そんな気持ちになりませんか?
簡単で効果的、しかもエコな this method は、ぜひ試してみる価値ありです。
さあ、今すぐ始めましょう!
不規則な動きで警戒心アップ!「風船設置」術
風船を庭に設置する方法は、その不規則な動きでハクビシンの警戒心を高める効果があります。子どもも楽しめる、遊び心満載の対策法なんです。
「えー、風船で本当にハクビシンが逃げるの?」と半信半疑の方も多いでしょう。
でも、実はこれ、結構効果があるんです。
ハクビシンは予測不能な動きを非常に警戒するんですよ。
それでは、具体的な設置方法と効果を見ていきましょう。
- 準備するもの
- 風船(明るい色や反射素材のものがおすすめ)
- ひも
- ヘリウムガス(浮かせる場合)
- 設置方法
- 風船を膨らませる(ヘリウムガスを使うとより効果的)
- ひもで風船を庭木や柵に結ぶ
- 地面から1〜2メートルの高さに設置
- 複数の場所に配置する
- 効果の仕組み
- 不規則な動き:風で揺れる風船がハクビシンを警戒させる
- 視覚効果:明るい色や反射素材が注意を引く
- 音の効果:風船同士が当たる音が不安を煽る
彼らは新しい環境の変化に非常に敏感で、特に予測できない動きを怖がる傾向があります。
風船のフワフワとした不規則な動きは、まさにハクビシンの警戒心をくすぐるんです。
「でも、風船ってすぐしぼんじゃわない?」という心配も当然ですよね。
そこで一工夫。
ヘリウムガスの代わりに普通の空気で膨らませた風船を使うのもおすすめです。
地面すれすれに這うように動く風船も、ハクビシンにとっては不気味な存在なんです。
ただし、注意点もあります。
強風の日は風船が飛ばされる可能性があるので、しっかりと固定しましょう。
また、環境への配慮も忘れずに。
割れた風船は必ず回収し、野生動物が誤って食べないようにしてください。
この方法の素晴らしいところは、見た目も楽しいこと。
お子さんと一緒に風船を膨らませて設置すれば、家族で楽しみながらハクビシン対策ができるんです。
「よし、今度の休みは風船作戦だ!」なんて楽しみになってきませんか?
ちょっと変わった方法ですが、意外と効果的。
そして何より、家族で楽しめる対策法なんです。
さあ、風船を膨らませて、楽しいハクビシン撃退作戦の始まりです!
光の乱反射で混乱!「古いCD吊るし」テクニック
使わなくなった古いCDを木に吊るす方法は、光の乱反射でハクビシンを混乱させる効果があります。リサイクル精神にあふれた、エコでクリエイティブな対策法なんです。
「えっ、CDってあのディスク?」と驚く方も多いでしょう。
そうなんです。
かつて音楽を聴くのに使っていたあのピカピカ光るディスクが、今や立派なハクビシン撃退グッズに大変身するんです。
では、具体的な設置方法と効果を見ていきましょう。
- 準備するもの
- 使わなくなったCD(DVD)
- 釣り糸やひもい>
- ワイヤーカッター(CDに穴を開ける用)
- 設置方法
- CDの端に小さな穴を開ける
- 穴に釣り糸やひもを通す
- 庭木や柵にCDを吊るす
- 地面から1〜2メートルの高さに設置
- 複数のCDを異なる角度で配置する
- 効果の仕組み
- 光の乱反射:太陽光や月光を不規則に反射
- 動きによる効果:風で揺れるCDが不安を煽る
- 音の効果:CDが風で揺れて出す音が警戒心を高める
彼らは光に敏感で、特に不規則に動く光源を不気味に感じるんです。
CDの表面が作り出す虹色の乱反射は、まさにハクビシンにとっては「なんだこれは?」という不可解な存在なんです。
「でも、近所の人から変な目で見られないかな…」という心配も当然ですよね。
そこで一工夫。
CDの裏面を使うのもおすすめです。
銀色の面なら、庭の装飾として違和感なく溶け込みます。
しかも、反射効果は十分あるんですよ。
ただし、注意点もあります。
強い日差しの下では、CDの反射光が周囲に迷惑をかける可能性があります。
角度を調整して、光が隣家や道路に当たらないようにしましょう。
また、CDの端は鋭利なことがあるので、設置時は軍手を着用するなど、安全に気を付けてくださいね。
この方法の素晴らしいところは、リサイクル精神にあふれていること。
使わなくなったCDに新たな命を吹き込むわけです。
しかも、風に揺られてキラキラ光るCDは、なかなかの景観にもなりますよ。
「よし、押し入れにしまってあるCDを引っ張り出してみよう!」なんてワクワクしてきませんか?
ちょっと変わった方法ですが、効果は抜群。
そして何より、家にあるものを再利用できる、エコな対策法なんです。
さあ、あなたの庭を、ハクビシンが寄り付かないキラキラ空間に変身させましょう!